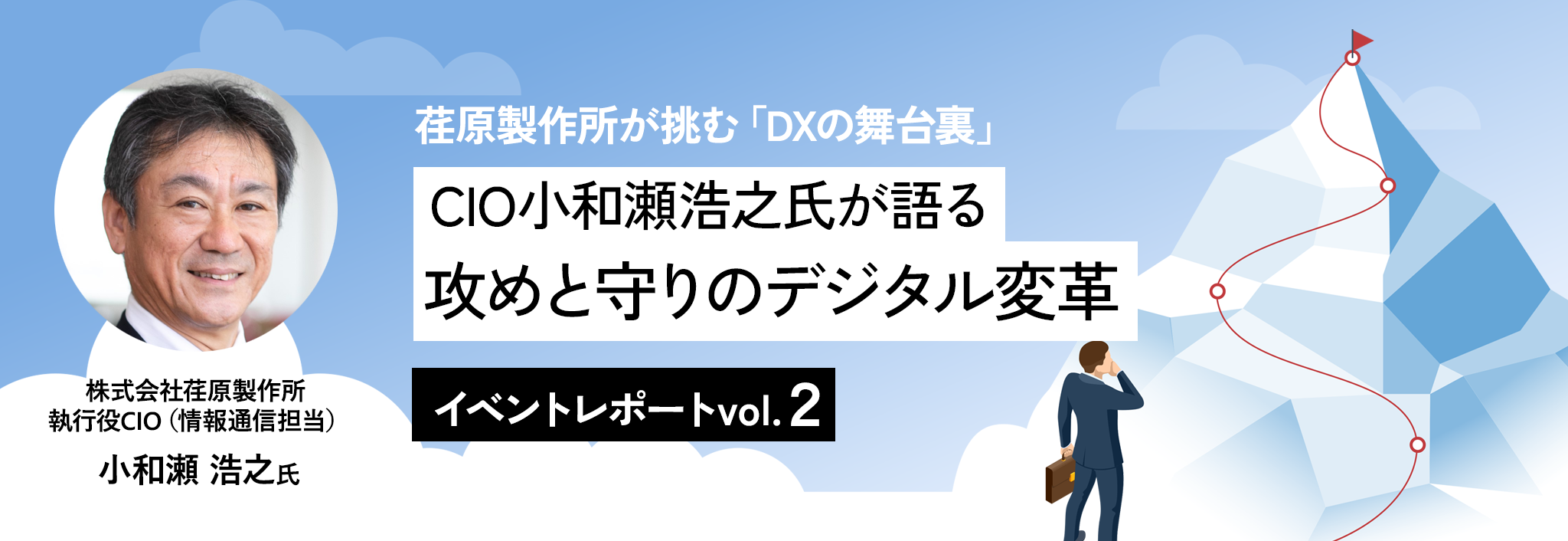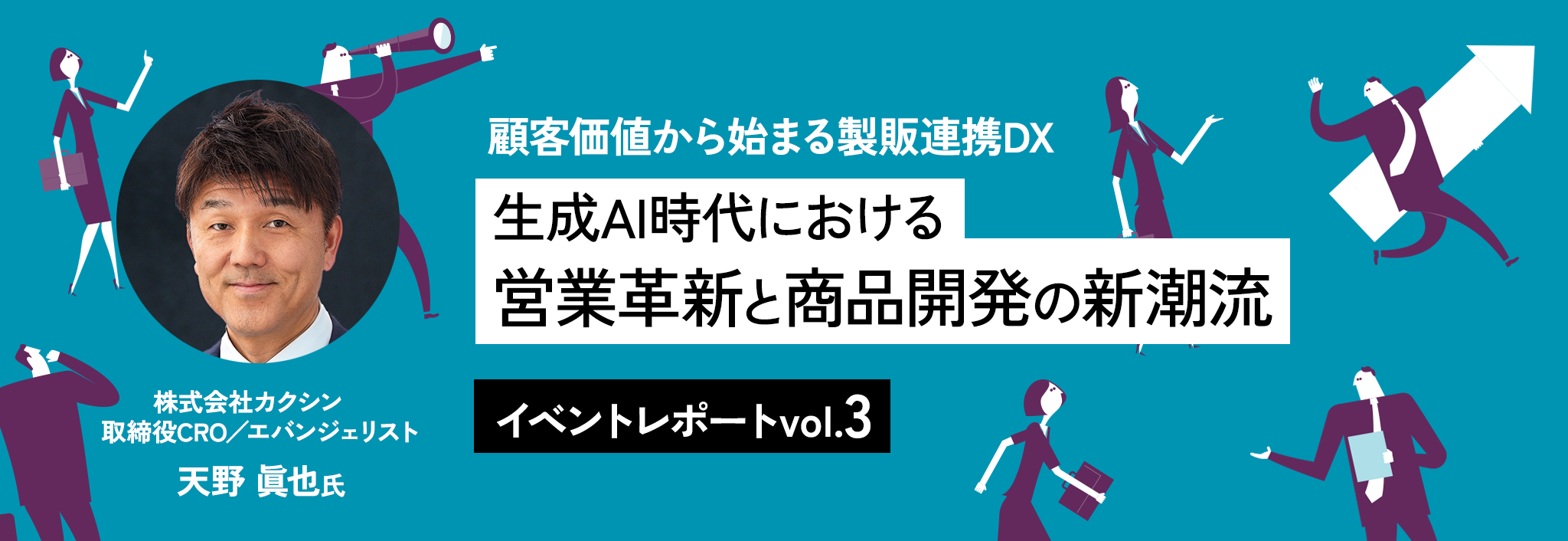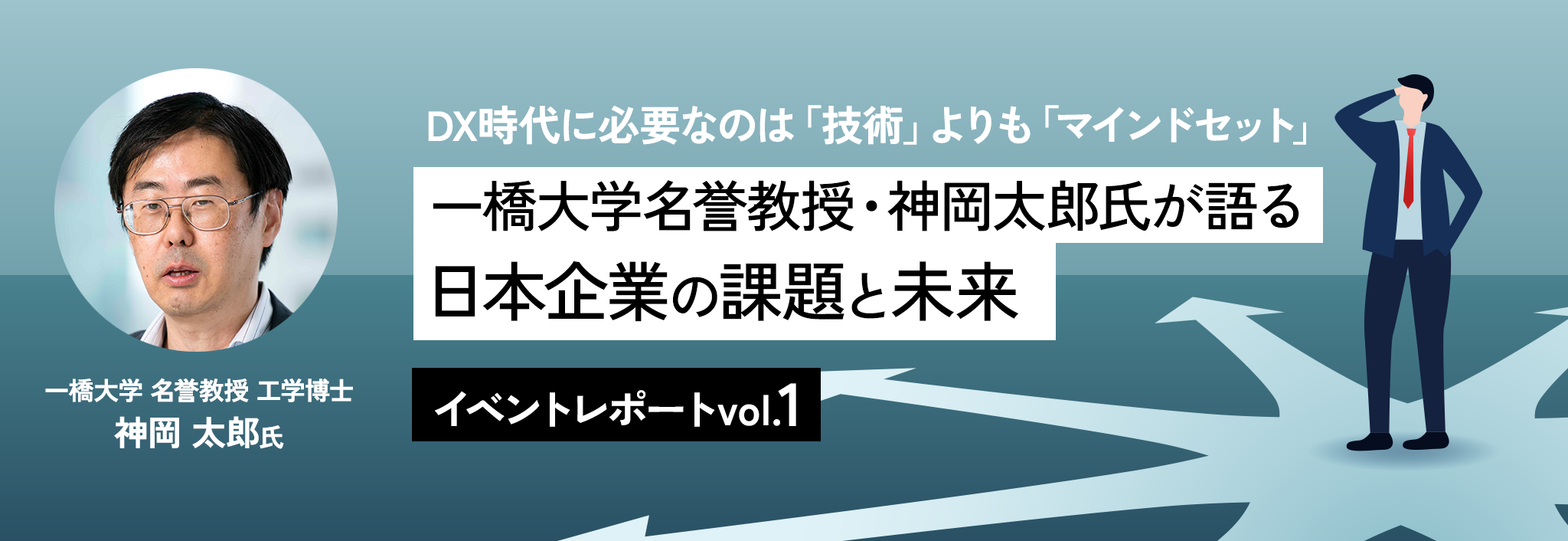
DX(デジタルトランスフォーメーション)が世界的な潮流となる中で、日本企業にとっての最適解とは何か。
単なるシステム導入や効率化ではなく、現場の強みを生かしながら変革を進める「日本流DX」が注目を集めています。
先日マクニカが2025年7月30日(水)に開催した「Executive Knowledge Sharing Forum~加速度を増す世界の変化の中で生き抜く――匠の知×デジタルの日本流 DX~」では、3名の登壇者がそれぞれの立場からDXを語り、日本流DXの在り方について多角的な視点を共有しました。
本記事では3本のコラムとして、それぞれの講演内容をお届けします。
【講演者情報】

一橋大学 名誉教授 工学博士
神岡 太郎氏
はじめに
デジタルトランスフォーメーション(DX)は単なる技術導入ではなく、企業文化や人材の意識を根本から変える営みである――。こうした問題提起が行われたのが、一橋大学名誉教授・神岡太郎氏の講演でした。
神岡氏は、大学で長らく経営とテクノロジーの関係を研究してきた人物であり、近年は「マインドセット」というテーマに特に注目していると語ります。自身が現場で見聞きしてきた事例や国際比較のデータを交えながら、日本がデジタル競争力で遅れを取る背景と、これからのDX推進に不可欠な意識改革の重要性を強調しました。

デジタル化の進展と日本の遅れ
講演の冒頭で神岡氏は、世界におけるデジタル活用の最前線を紹介しました。たとえば、ノルウェーのエネルギー企業が携帯端末を用いて石油掘削船のバルブの状態をリアルタイムで監視・操作できる「デジタルツイン」の事例です。スマートフォンから仮想空間を操作すると、それに連動して現実のプラント設備が動く。この光景は、数年前に同氏が最も衝撃を受けた出来事のひとつだといいます。こうした事例が示すのは、デジタル活用が単なる効率化ツールにとどまらず、産業構造そのものを変えているという事実です。自動車の車内を見れば、アナログ機器は減り、デジタル機器が標準となっていることからもその変化は明らかです。
一方で、日本は依然として「デジタル後進国」と位置付けられています。スイスのビジネススクールIMDによる「世界デジタル競争力ランキング」では、日本は67カ国中31位にとどまっており、特に人材スキルに関しては最下位の67位という厳しい評価です。この結果を受け、神岡氏は「特に開発人材については、 大学等の高等教育機関が十分にコンピュータサイエンス等の教育を行ってこなかったツケが回ってきている」と語りました。自動車産業のデジタル対応力を評価したランキングでも、日本企業はトップ15に入っていません。これは製品の品質に定評があるにもかかわらず、デジタルを駆使した付加価値創出では遅れを取っていることを示しています。
技術よりもマインドセットの問題
では、なぜ日本はここまで立ち遅れてしまったのでしょうか。神岡氏は「制度」と「マインドセット」の問題を最大の要因に挙げました。
「DXをやっている」「AIを導入している」という特別意識のままでは、本質的にデジタルを活かすことはできない。むしろ、ビジネスを進めるうえでデジタルが自然に組み込まれる状態、つまり“DXアズ・ユージュアル(DXが日常化した状態)”を実現できるかどうかが重要だと強調します。
特に注目すべきは、国民的なマインドセットの違いです。海外の企業や学生が新しい挑戦に積極的であるのに対し、日本では「失敗を避ける」意識が強く、新しいやり方に踏み込むことをためらう傾向があります。神岡氏は「技術力が劣っているのではなく、マインドセットのあり方が問題だ」と断言しました。
グロースマインドセットとフィックスマインドセット
講演の中心テーマとなったのが「グロースマインドセット」と「フィックスマインドセット」という考え方です。
心理学者キャロル・ドゥエック氏の研究に基づくこの概念では、グロースマインドセットを持つ人は「努力すれば能力は伸びる」と信じ、挑戦や失敗を前向きな学びとして受け止めます。対照的にフィックスマインドセットの人は「能力は固定的で変わらない」と捉え、他人の成功を脅威と感じる傾向があるといいます。
神岡氏は自身の経験を踏まえ、日本と海外の学生の姿勢の違いを具体的に語りました。中国の大学で授業を行った際、学生から2時間にわたって質問攻めにあったエピソードを紹介。その熱意と主体性に、日本の学生との大きなギャップを感じたといいます。日本の授業では、せいぜい数分程度の質問がある程度であり、この違いが将来の競争力に直結するのではないかと危機感を示しました。
海外企業との比較 ― 変革を主導する文化
海外では企業トップが自ら「グロースマインドセット」を旗印に掲げ、全社的な文化変革を推進する事例が目立ちます。マイクロソフトのCEOサティア・ナデラ氏はその代表例であり、「我々には誰もが成長できると信じる文化が必要だ」と社内外に発信。こうしたリーダーシップが、同社の復活を支えた大きな要因と評価されています。
神岡氏は「比較的短い時間グロースマインドセットを持たせることは可能だが、それだけでは一過性に終わってしまう。持続的に根付かせるには、組織文化として定着させることが必要だ」と強調しました。
自ら挑むDXへ
神岡氏はさらに、日本企業の現状を「やらされDX」と表現しました。企業がDX研修を実施しても、多くの社員が「やらされ感」を抱き、自発的に取り組む姿勢が不足しているというのです。
背景には、日本企業文化における「忠誠心・ロイヤリティー」の高さと「エンゲージメント」の低さがあります。上司の指示には忠実に従う一方で、自ら考え挑戦する意識は低い。この構造がDX推進を阻害していると分析しました。
同氏が実施した調査でも、「デジタルを活用することで新しい価値を創造できる」と信じる“デジタル・グロースマインドセット”を持つ人材ほど、DXに積極的に取り組む傾向が確認されています。つまり、マインドセットの違いがDXの成果に直結しているのです。
DXの出発点は「マインドセット」と「カルチャー」
講演の締めくくりに神岡氏は次のように語りました。
「新しいDXの時代は、技術そのものではなく、まずマインドセットやカルチャーをトランスフォーメーションするところから始めるべきだ」
つまり、デジタルツールの導入やシステム刷新といった“手段”に先行して、社員一人ひとりが「挑戦を楽しむ文化」を持つことが必要不可欠だというメッセージです。
DXは単なる効率化のための技術導入ではなく、企業と人材が未来を切り拓くための意識改革である――。この視点が、今後の日本企業にとって最大の成長のカギとなるでしょう。

おわりに
神岡氏の講演は、日本企業がDX推進で直面している「本質的な壁」を浮き彫りにしました。それは技術力不足ではなく、「マインドセット」と「文化」の問題です。
挑戦を恐れず学び続ける「グロースマインドセット」をいかに育むか。その問いに真剣に向き合えるかどうかが、今後の日本経済の行方を左右すると言えます。
日本流DXを多角的に捉える本シリーズ。次回は株式会社荏原製作所 CIO(情報通信担当)小和瀬 浩之氏の講演をレポートします。
実際の現場でDXがどのように進められているのか、その舞台裏に迫ります。
▼こちらからご覧いただけます▼