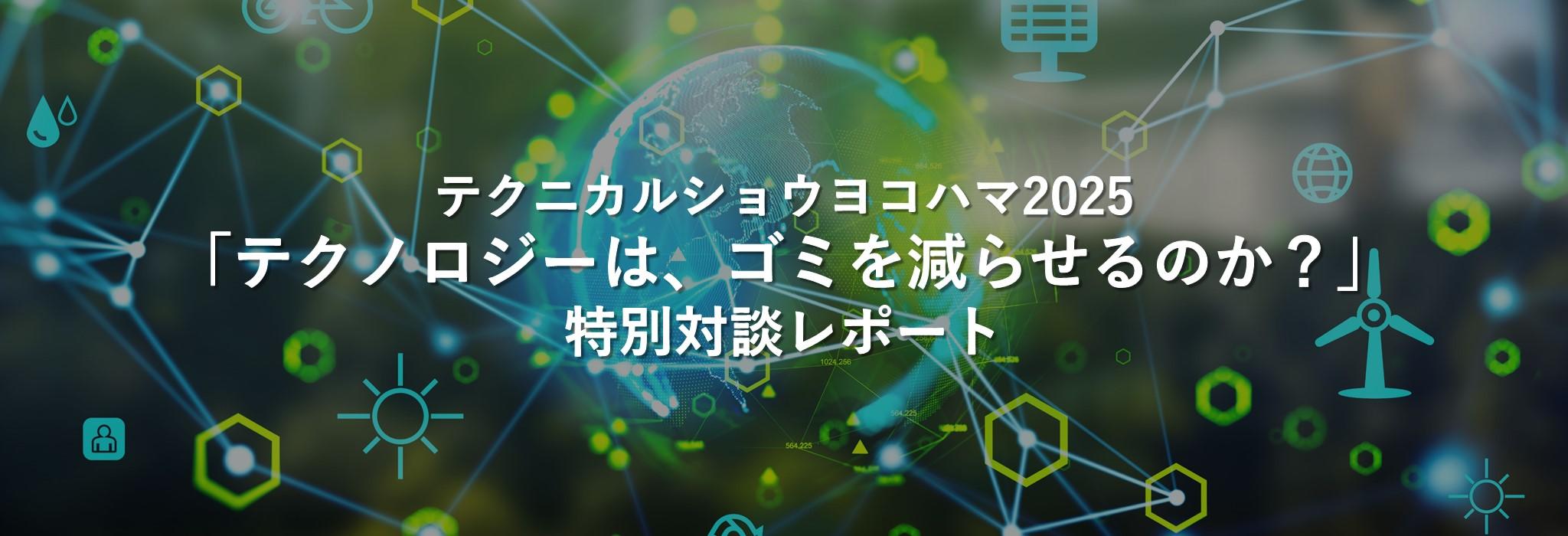
2025年2月5日から7日までの3日間、パシフィコ横浜で「テクニカルショウヨコハマ2025」が開催されました。同イベントは神奈川県下最大級の工業技術・製品に関する総合見本市となっており、2025年も「技術を創る 未来を創る」をテーマに、さまざまな企業が出展していました。
本記事ではゴミ清掃員としてのキャリアをもつ「清掃芸人」こと滝沢秀一氏(マシンガンズ)、マクニカの代表取締役社長である原一将、そして当日に急遽駆けつけてくださった神奈川県知事の黒岩祐治氏の3名が展示会場内特設セミナー会場でおこなった、特別対談のレポートをお届けします(内容は一部を抜粋したものです)。
▲会期初日、早い時間の開催だったにもかかわらずほぼ満席に。「ゴミを減らす」というテーマに関心のある方が多かったことがうかがえます。
第1部(滝沢氏×黒岩氏×原)
冒頭はファシリテーターの滝沢氏による挨拶からスタート。「僕は芸人を27年間やるかたわらで、ゴミ清掃員としても働いています。もともとやりたくて始めた仕事ではなかったのですが、働くうちにゴミの問題について真剣に考えるようになり、見えかたが変わってきました。」
そこへ黒岩氏が「いまの脱炭素社会において、やはりゴミをどうするかは大きな問題ですよね。分別なども皆さんに自然にやってもらい、その流れを定着させていくことが大事です。」と続けます。
つぎに滝沢氏が「ゴミ清掃員になって衝撃を受けた」エピソードを披露。1台の清掃車で集められるゴミはおよそ2tで、それが1日6往復で10~12tものゴミを回収していること、環境省のホームページでは、日本の最終処分場の寿命が23~4年と言われていることなどが解説されました。
「こうした現状に、なにか対策などはありますか」と滝沢氏が尋ねると、黒岩氏は神奈川県が実施した「かながわプラごみゼロ宣言」を紹介。すべてのプラごみのリサイクルを目的としたもので、2018年、鎌倉市の由比ヶ浜の海岸に打ち上げられたシロナガスクジラの赤ちゃんの胃からプラごみが出てきたことが発端でした。
黒岩氏は「海にただようゴミは、皆さんの生活で出たものが陸から流れていくことがほとんどです。なるべくゴミを出さなくしたり、リサイクルをしてほしいですね。」と述べました。これに続き、「日本の廃プラスチックは行き先をなくしていて、色々なリサイクルが行われていますが、それも十分ではありません。最終処分場のキャパも超えそうとなると、リサイクルに関わるテクノロジーを早急に開発しなければならない、待ったなしの状況だと思います。」と原がコメント。
滝沢氏が会場に「あと23~4年でゴミを捨てられなくなることを知っていた方、どのくらいいらっしゃいますか?」と尋ねたところ、挙手したのは10名以下でした。まずは、こうした現状を知ることが重要だと言えそうです。
テーマは変わり、港区の可燃ごみ組成割合のデータなどを交えながら滝沢氏が分別の大切さを解説。たとえば紙類は28.1%のうち16.1%は資源として分別でき、「もう一度紙として生まれ変わるか、灰になるかでまったく真逆である」ことなどを強調しました。プラスチック類についても同様で、16.8%のうち9.0%は再利用が可能です。仮にこの16.1%と9%が資源として活用されれば25~30%ものゴミがなくなり、1億人で取り組んだ場合は3億のゴミを2億に減らせるわけです。「やはりみんなで協力してやることが大事だと僕は思います」と滝沢氏。
分別について意見を求められた黒岩氏は、「ナッジ理論(※)」を利用した神奈川県の取り組みを紹介。湘南ベルマーレ付近で提供される食事の容器として洗ってリユースできるものを用意し、「Aの容器」 「Bの容器」と仮に命名。それを交えて利用者にクイズのような形式でゴミを捨ててもらったところ、90%以上の人が(無意識に)分別してくれたそうです。
※人間の行動心理を利用し、相手に気づかれないうちに望ましい行動を促す理論。
それにつなげて原は、展示中の廃プラスチック油化装置に触れ、 「我々としてのポイントは、やはりテクノロジーでいかにリサイクルを実現するかです。今回の展示会では、廃プラスチックを油に変えるKASHIN INFINITYを展示しています。ゴミの減量をしつつ、分散型の資源循環を可能にする装置です。」と、プラスチックのリサイクルに対するマクニカの取り組みを語りました。
滝沢氏は続けて、地域によるプラスチックごみの扱いの違いや、「プラスチック中間処理場」における手作業での仕分けの大変さなどを力説。弁当の容器で汚れなどが付着している場合、資源として再利用できるプラスチックであっても、可燃ゴミとして焼却しなければならないことも少なくないようです。さらに「ただ、それらを固めれば着火剤のように扱える場合もあるので、政府が住民にあらかじめ周知し、捨てるときに少しでも分別を意識してもらうことが大切な活動だと思います。」とコメントしました。
また、日本はアメリカに次いで世界で二番目にプラスチックごみの排出量が多く、海外に輸出せざるを得ない現状についても解説。たとえば、マレーシアに資源としてプラスチック送ることがありますが、それらに意外と汚れが付着しており、送り返されることもあるんだとか。そして、その過程で漏れ出たゴミが途中で流され、川を汚している現状を紹介。ゴミの問題が日本だけではなく世界の問題になっているのには、こうした背景もあることが分かりました。
「やはり、そもそもゴミをなくすことが大切ですよね」と述べる黒岩氏は、過去の「SDGs大賞」に投稿された子どもの4コマ漫画を見て、昭和以前の時代を連想したといいます。現代ではスーパーに行くと大半の商品がビニールで包装されていますが、かつては魚屋さんで魚を買うと新聞紙で包んでくれたり、豆腐は鍋を持って買いに行ったりしていました。牛乳もビンが主流でしたが、今ではそれがパックになっています。
「ゴミが増えているのは、便利さをひたすら追い求めた結果ですよね。ペットボトルも当然のように使われていますが、昔のようにみんなが水筒を持てば、ペットボトルはいらなくなるわけです。出たゴミをどうするかを考えることも大事ですが、不要なゴミの発生をなくす努力もしなければならないでしょう。」と黒岩氏は続けました。また、「マクニカのKASHIN INFINITYのような機械による分散処理が、今後のゴミ処理におけるひとつのコンセプトになる」ともコメント。
最後は滝沢氏が「ゴミが一点に集中すると国内ではすべてを処理しきれなくなるため、分散がポイントになりそうですね」と締めくくり、第一部が幕を閉じました(黒岩知は所用のため、ここで降壇)。
第2部(滝沢氏×原)
第2部は、滝沢氏による感染廃棄物の処理の経験談から始まりました。新型コロナウイルス感染症が世界で猛威を振るっていたころ、病院は法律によってゴミを厳重に梱包して処分していました。
しかし、一般の家庭ゴミではそんなこともなく、滝沢氏も含めて回収する清掃員は生身です。また、ゴミが鳥や猫などに荒らされて中身が飛び散っていれば、感染の危険度が高まります。マスクも買い占められているため、つけることができません。まさに「命がけの仕事」と言っても過言ではなく、ときには回収先の人から書き置きで感謝をされることもあったそう。
そんな修羅場を経験した滝沢氏が、原に質問します。「こうした課題は法律だけでなく、テクノロジーでも解決できるのではないかと思っています。マクニカは僕が経験した苦労を解決してくれる可能性があるものを開発したんですよね?」
「はい。それが乾燥減容機メルトキングです。産業廃棄物や食物残渣を間接加熱によってサラサラの粉にし、容量を5分の1から50分の1にまで減らせる画期的な装置です。」と原。
仮に1t(1,000kg)が50分の1まで減れば、わずか20kgになる計算です。感染性廃棄物でも熱処理によって無害化されるため一般廃棄物として処分できるようになったり、重量が軽くなることによって運搬費が減ったり、運搬時に排出されるCO2が削減されるなどのメリットがあります。また、原は食物残渣を処理した粉を二次発酵して肥料として使えたり、ゴミを袋のまま投入できることなども解説しました。
滝沢氏はこれに「今後は超高齢化社会で、高齢者向けの施設などでもオムツなどのゴミが増えてくると思いますが、清掃員にとってもすごく安心ですよね。メルトキングは大きな施設であればあるほど導入すべきですね」と返します。
話題はKASHIN INFINITYへ移り、「どういった施設で特に活躍するのですか?」と滝沢氏が質問。原は「幅5メートル、高さ3メートル、奥行き2メートルというコンパクトさがウリなので、色々なところに置けます。用途はさまざまですが、大量のゴミを集めた処理所向けではなく、あくまで自分の会社や事業所などで廃プラスチックをその場でエネルギーに変えられるというのがコンセプトです」と答えます。
たとえば、ペットボトルのキャップであれば約4時間で重油に変わるとのこと。また、ホテルチェーンの事業所に設置することで歯ブラシをA重油相当の油に戻し、その油をお風呂を沸かす燃料として使う……といったことが想定されます。さらに、成分分類によってA重油相当の油だけでなく灯油やガソリンに分けることも可能。この説明を聞き、「やっぱり、循環ってこういうことですよね。重油や石油の価格は世界情勢に左右されますし、今後の社会では大事なことですね。」と感心する滝沢氏。
「先ほど黒岩知事がおっしゃったように、まず入口でゴミをなくすことは重要です。そして、出口ではテクノロジーによってゴミを資源に変えると。このように入口と出口両方の戦略があってはじめて、SDGsを達成できるのではないかと思います」と原は続けました。
滝沢氏も「最終処分場の切迫問題」と「資源になるものを燃やさず、お金や自分たちが利用できるものに換えること」の2つをシステム化して解決することが重要だとしつつ、鹿児島県の「大崎リサイクルシステム」という取り組みを紹介。
これは、あえて焼却炉を立てないことで年数億円単位の維持費をなくし、既存の埋め立て処分場の延命化を図る措置です。浮いたお金や資源として売却できるものを売って得られた利益は奨学金に回され、奨学金援助を受けた学生は一定年数以内に大崎町に戻ってくると、利子の返済は不要に。
「すべての自治体はこうなるべきだと、僕は個人的に思っています。今後、超高齢化社会になるのであれば、福祉費に充ててもよいでしょう。通常、ゴミが減るとそのぶん従業員も減らされることになりますが、大崎町の場合はその資金で雇用も生み出しています。ゴミ屋ではなく、リサイクル屋へと雇用の仕方を変えているのです。」と滝沢氏は述べました。
対談はいよいよ終盤へ。「ゴミを価値に変えれば変えるほど、その価値が新たなものを生んだり、循環型の経済社会を作っていますから、発想の転換が大事ですよね。そこに対してテクノロジーを提供し、お手伝いができればと考えています。」と原。
滝沢氏は「アメリカの格言に、ゴミは想像力の欠如にしか過ぎないというものがあります。つまり、想像力がないからすべてがゴミになってしまうけれど、資源になるという観点を突き詰めていけばゴミという言葉はなくなるはずなんです。たとえゴミだとしても、適切な捨て方や燃やし方があります。ですから、今後SDGsを進めていくうえでは、人権や環境のことを総合的に考えていくことがもっとも大切だと思います」と続けました。
最後に、滝沢氏からメッセージを求められた原は「今日はありがとうございました。当社もいち企業として、まだまだ取り組むべきテーマが多くあることを勉強させていただきました。知ることを知ったうえで、ゴミをゴミでなくすという発想のもと、想像力をもって新しい価値を作るための発信をしていきたいです。滝沢さんとも、末永くパートナーとして歩みたいですね」とコメント。滝沢氏は「ぜひ一緒に何かできたらいいですね」と返しました。
