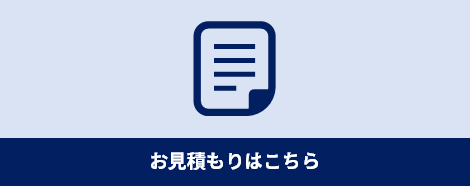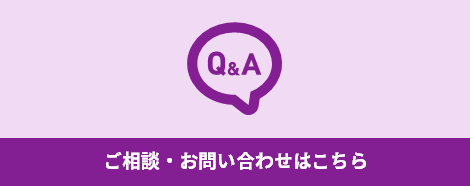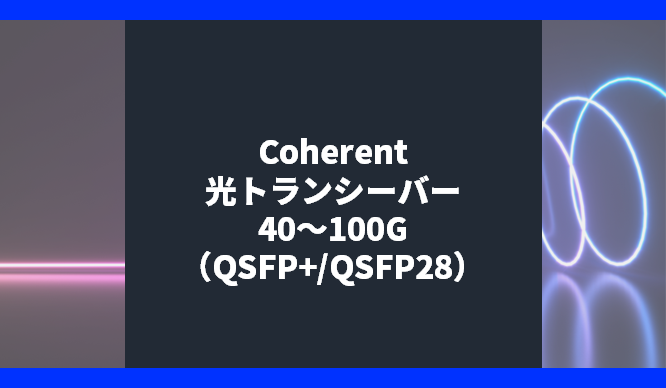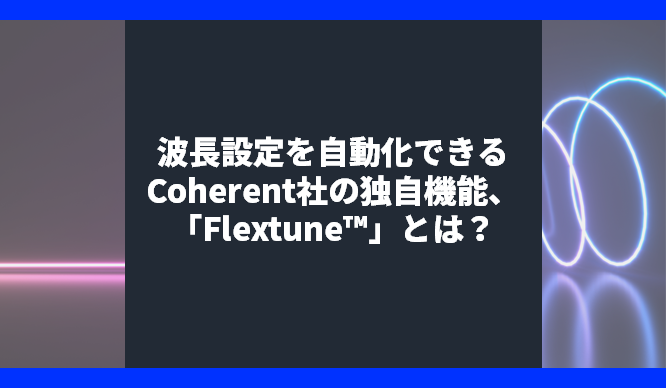光トランシーバーモジュールは、光伝送ネットワークを構成する重要なコンポーネントの1つです。これまでに高速化や小型化の要望に応えていろいろと変化してきたため、さまざまな種類があります。
本記事では、現在データセンターや光通信の分野で多く使用されている100GbE光トランシーバーモジュールに着目し、その歴史を振り返りつつ100GbEの規格について深堀りします。
高速化・小型化する光トランシーバーモジュール
最初に1GbE(1Gbps Ethernet)に対応した光トランシーバーモジュール、GBIC(Gigabit Interface Converter)が規格化されたのは1995年です。もう30年近く前のことです。それ以来、光トランシーバーモジュールは伝送スピードの高速化や小型化への要望に対応してきました。
現在では、SFP(Small Formfactor Pluggable)というモジュール規格(=フォームファクター)が主流となっており、伝送スピードに応じていくつかのタイプがあります。
|
伝送速度(GbE) |
SFPフォームファクター |
|
1 |
SFP |
|
10 |
SFP+ |
|
25 |
SFP28 |
|
40 |
QSFP+ |
|
100 |
QSFP28 |
表1. 伝送スピードとSFPフォームファクター
100Gでの主流はQSFP28
100G化議論は2006年からスタートしていましたが、2010年に40GbEとともに100GbEが2010年に標準化されました。当初の100GbEは、電気側の10GbE信号を10レーン束ねて100GbE(10GbE×10レーン)とする「CFP」と「CFP2」が規格化され、その後に25GbEを4レーン束ねた(25GbE×4レーン)「CFP4」と「QSFP28」が規格化されました。
|
1レーン当たりの速度とレーン数(電気側) |
フォームファクター |
|
10GbE×10レーン |
CFP |
|
CFP2 |
|
|
25GbE×4レーン |
CFP4 |
|
QSFP28 |
表2. 複数のレーンを束ねて100Gに対応
100GbEではQSFP28の市場流通量が圧倒的に多いために、供給性やコストを考えてQSFP28に切り替えるユーザーが多くなっています。結果として、100Gに対応した光トランシーバーモジュールのフォームファクターは「QSFP28」が主流となっています。
たくさんある100G光トランシーバーモジュールの光伝送規格
モジュール規格のご紹介の次は、光側の伝送規格を解説します。表3に光の伝送規格をまとめました。
表は縦軸に通信距離、多芯の光ファイバーを用いる「多芯光ファイバー」、2芯の光ファイバーを用いる「2芯光ファイバー」に分けています。横軸は通信距離よって、マルチモード光ファイバーを用いるもの、シングルモード光ファイバーを用いるものを分類しています。表3にご覧いただけるように、たくさんの光伝送規格があります。
|
通信距離 |
多芯光ファイバー (MPOコネクター) |
2芯光ファイバー (LCコネクター) |
|
|
Multi-mode Fiber |
100m |
100GBASE-SR10 (IEEE802.3ba) – CFP/CFP2 100GBASE-SR4 (IEEE802.3bm) – CFP4/QSFP28 100GBASE-SR2 (IEEE802.3cd) - SFP-DD |
100G SWDM4 (SWDM Alliance) – QSFP28 100G SRBD (Cisco, ARISTA) – QSFP28 |
|
300m |
100G-eSR4 (各社独自) – QSP28 |
||
|
Single-mode Fiber |
500m |
100G PSM4 (100G PSM4 MSA) QSFP28 |
100G CWDM4-OCP (Facebook) – QSFP28 100GBASE-DR (IEEE802.3cd) – SFP-DD |
|
2km |
- |
100G CWDM4 (CWDM4 MSA) – QSFP28 100G FR (100G Lambda MSA) - SFP-DD |
|
|
10km |
- |
100GBASE-LR4 (IEEE802.3bm) – CFP4/QSFP28 100G eCWDM4 / 4WDM-10 (4WDM MSA) – QSFP28 100G LR (100G Lambda MSA) – SFP-DD |
|
|
20km |
- |
100G eLR4 / 4WDM-20 (4WDM MSA) – QSFP28 |
|
|
40km |
- |
100GBASE-ER4 (IEEE802.3bm) – CFP2 100G ER4f / 4WDM-40 (4WDM MSA) – QSFP28 |
|
|
80km |
- |
100G ZR4 (各社独自) – QSFP28 100G COLORZ (Inphi) – QSFP28 |
|
|
120km |
- |
100G DCO (各社独自) – CFP2/QSFP28 |
表3. 100G光伝送規格まとめ
これらの規格は、以下のような団体によって標準化・策定されています。
・米国電気電子学会のIEEE802.3 Ethernet Working Groupで標準化される
・いくつかの光トランシーバーモジュールメーカーによるMulti Source Agreement(MSA)やその他のアライアンスで策定される
・メーカー各社の独自規格
MSA規格については、下記でも少しご紹介します。
伝送距離でみる3つの代表選手・・・100GBASEのSR4、LR4、ER4
100GbEの光トランシーバーモジュールとして代表的なものに、短距離用のSR4、長距離用のLR4、さらに長距離用のER4があります。
一つ目の短距離用SR4から解説を始める前に、まずは最初に実現した100GbE光トランシーバーモジュール「SR10」を見てみましょう。
最初に実現された100GBASE-SR10
「100GBASE-SR10」(*1)は、24芯のリボンファイバーを使用して100mを伝送する「100GBASE-SR10」という規格で、フォームファクターはCFPもしくはCFP2でした。
(*1)IEEE802.3で標準化された規格、または標準化に向けて議論中の規格は「100GBASE」と呼びます。
SR10のSは短距離(Short)を意味します。SR10の10は、光信号が10レーンであることを示します。つまり、光信号は10GbE×10レーンで構成されています。
レーン数が4つになった、短距離用100GBASE-SR4
そこから技術が進み、25GbE×4レーンで構成される「100GBASE-SR4」が標準化されました。SR4の4は、光信号が4レーンであることを示します。つまり、光信号は25GbE×4レーンの構成です。
発光レーザー素子、および受光器がそれぞれ10個(SR10)から4個(SR4)に減り、小型化が大きく進みました。フォームファクターはCFP4もしくはQSFP28で、SR10と同様に100mを伝送します。現在、100m以内の短距離接続にはこのQSFP28 100GBASE-SR4(図1)が多く使用されています。
図1. 100G SR4ブロック図
長距離用の100G LR4と、超長距離の100G ER4
続いて、長距離接続用として光信号4レーンで10kmを伝送する「100GBASE-LR4」、40kmを伝送する「100GBASE-ER4」が標準化されました。LR4のLは長距離(Long)、ER4のEは拡張された長距離(Extended)を意味しており、2芯の光ファイバーで伝送します。
100mを伝送するSR4ではリボンファイバーを使うと記載しましたが、10kmや40kmのような長距離を伝送するLR4やER4では、リボンファイバーを使うことは運用やコストにおいて現実的ではありません。
そのため、WDM(Wavelength Division Multiplexing:波長分割多重)という技術を使って、4レーンの光信号を多重して1本の光ファイバーで送ります(図2)。
この技術は、4レーン分の光の波長を少しずつずらし、光合波器(MUX)で1本の光ファイバーに4つの異なる信号を多重しているのです。一方、受信側では光分波器(DeMUX)により、異なる波長ごとに分離して各レーンの信号に分けることができるようになっています。WDMの詳細については、こちらをご覧ください。
図2. 100G LR4・ER4ブロック図
光トランシーバーモジュールのコストを下げるために、多くの光伝送規格でエラー訂正をおこなうFEC(Forward Error Correction)が採用されています。FECでは、エラーを検出・訂正するための冗長ビットを送信側で付加して、伝送中に発生したエラーの訂正を受信側でおこないます。FECを使用することで、光部品のコストを低減できるメリットがあります。
しかし、LR4ではFECを使うように定めていません。FECを使用しないで伝送距離を10kmに伸ばすために、高性能なレーザーと受光器を使用しています。
さまざまな要望に対応したMSA規格
上でも少し触れましたMulti Source Agreement(MSA)規格とは、複数のメーカーによって合意された、光トランシーバーモジュール製品に関する規格です。そのMSA規格を3つピックアップしてご紹介します。
1. 100G CWDM4
Hyper Scale Data Center など多くのユーザーから、SR4の伝送距離100mでは足りない、でもLR4の10kmまでは必要ない。さらにより安価だとうれしい・・・という要望がありました。これらの要望を満たす100G光トランシーバーモジュールとして、伝送距離が2kmである「CWDM4」が提唱されました。
LR4ではレーザーの波長間隔が800GHz(約4nm)であったのに対して、CWDM4では波長間隔を20nmと広くしたため、複雑な波長制御機構が不要となりました。(図3)
また、伝送距離も10kmから2kmに制限することで、高価なレーザーでなく廉価なレーザーを使えるようになりました。
図3. LR4とCWDM4の波長配置
2. 100G ER4f
長距離用である100GBASE-LR4の説明で、LR4ではFECを使うよう定めていない、という話をしました。同じく拡張された長距離用のER4でも、FECを使うように定めていません。FECを使用しないで伝送距離を40kmに拡張するために、さらに高性能なレーザーと受光器を使用しています。
しかし、ER4にFECを適用して小型化・低コスト化を実現したのがER4f(または4WDM-40)というMSA規格です。「QSFP28 100G ER4」として販売されている光トランシーバーモジュールをWeb上で見かけることがありますが、そのほとんどはFECなしでは40km伝送できず、25km〜30kmが限界です。つまり、ER4と言いながら実態は「ER4f」であるので注意が必要です。
図4. LR4とER4を低コスト化したCWDM4とER4f
3. 100G SWDM4
SR4では12芯のリボンファーバーを使って100mを伝送します。リボンファイバーでなく2芯のマルチモードファイバーで伝送したい、という要望に応えるために提唱されたのがSWDM4です。
2芯のファイバーで伝送するために、これまで長波長帯の技術だったWDMを短波長帯に適用したものが「100G SWDM4」です。
100G SWDM4の最大のメリットは、2芯マルチモードファイバーを使う10G SRからファイバーを張り替えることなく、10Gから100Gにアップグレードすることができることです。
どちらも、2芯のマルチモードファイバーを使う伝送であるために、ファイバーをそのまま流用できるのです。
図5. SR4にWDM技術を適用したSWDM4
40km以上への対応も
100G ER4fは40kmを伝送しますが、さらに光の送信パワーを上げて、受信感度を向上させることで長距離化を図ったものに、ZR4があります。ZR4のZはExtendedのEよりもさらに長距離であることを意味し、4は4レーンをWDMしていることを表します。
そして、ZR4よりもさらなる長距離化を実現する100G ZRも登場しています。100G ZRのZは、ZR4と同じく超長距離を表すのですが、その後ろにER4やZR4にあった4が付いていません。これは、ER4やZR4のように、4つの波長をWDMで波長多重するのとは違った方法で、光を伝送しているためです。具体的には100G ZRではDP-QPSKという変調方式を採用して1つの波長のみで光を伝送しています。100G ZRについては、また別の記事で詳しくお伝えするようにしたいと思います。
100G光トランシーバーモジュールの伝送規格について解説しました
この記事では、光トランシーバーモジュールの100GbE光伝送規格に焦点をあてて説明しました。400G編、800G編の記事もございますので、是非ご覧ください。
400G編:https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/coherent/144904/
800G編:https://www.macnica.co.jp/business/semiconductor/articles/coherent/145049/
マクニカでは、光トランシーバーモジュールのリーディングカンパニーである Coherent社のFinisar Transceiverシリーズをご提案しております。経験豊富な営業と光トランシーバーモジュール製品専属の技術スタッフがお客様の検討から導入、運用までを一貫してサポートします。ご興味のあるお客様は、ぜひ以下のフォームよりお問い合わせください。