耳で聞こえる“音”は、どうやって生まれるのか?
私たちは日々、音に囲まれて生活しています。人の声、音楽、車のエンジン音、風の音——それらはすべて「耳で聞こえる」ものですが、実際には空気の中を伝わる“振動”です。けれども、「音って何?」と改めて聞かれると、意外と説明できないものです。
音声技術や音響設計に関わる人にとって、「音をどう処理するか」以前に、「音とは何か?」を理解することはとても重要です。なぜなら、音の性質を知らなければ、マイクで拾った信号が何を意味しているのか、スピーカーから出る音がどう伝わるのかを正しく捉えることができないからです。
本記事では、まず「音とは何か?」という基本に立ち返り、音波のしくみと人間の聴覚の働きをやさしく解説します。音声開発の入り口として、そして Audio Weaver のような汎用的なオーディオ開発ツールを使いこなすための土台として、ぜひ一緒に“音の正体”を探っていきましょう。
音とは何か?空気の中を伝わる“波”の正体
私たちは、目を閉じていても音で世界を感じ取ることができます。
誰かの声、風の音、遠くで鳴るサイレン——それらはすべて、空気の中を伝わってくる“振動”です。たとえば、ギターの弦を弾くと、弦が震え、その震えが空気を押し広げたり引き戻したりします。この空気の“押し引き”が波のように広がって、やがて私たちの耳に届きます。これが「音」です。このように、音は空気の中を伝わる波(音波)であり、目には見えませんが、確かに存在する“動き”です。そしてこの波は、空気の粒子が振動方向と同じ方向に揺れるという特徴を持っており、これを縦波(たてなみ/じゅうは)または疎密波(そみつは)と呼びます。
※縦波についてもっと詳しく知りたい方は、以下の解説ページも参考になります。
音波にはいくつかの特徴があります。
・周波数 (Hz):1秒間に何回振動するか。音の「高さ」に関係します。
・振幅:波の大きさ。音の「大きさ(音量)」に関係します。
・音速:音が空気中を伝わる速さ。気温 20℃ では約 340m/s です。
これらの性質を理解することで、音を“感じる”だけでなく、“扱う”ことができるようになります。次のセクションでは、この音波を人間の耳がどのように感じ取っているのか、聴覚のしくみを見ていきましょう。
音の感じ方には“3つのポイント”がある
私たちは音を聞いたとき、「高い」「大きい」「きれい」など、さまざまな印象を受けます。実はこの印象は、音の持つ3つの性質によって決まっています。
① 高さ(周波数)
音の「高さ」は、空気の振動の速さ = 周波数 (Hz) によって決まります。周波数が高いほど「高い音」、低いほど「低い音」と感じます。たとえば、ピアノの高音鍵は周波数が高く、低音鍵は周波数が低いです。
② 大きさ(振幅)
音の「大きさ」は、振動の強さ=振幅によって決まります。振幅が大きいほど、空気の圧力変化が大きくなり、「大きな音」として感じられます。逆に振幅が小さいと「小さな音」になります。
③ 音色(波形の複雑さ)
同じ高さ・大きさでも、楽器によって音の印象が違うのは、音色(おんしょく)が異なるからです。これは、音波の波形の複雑さや、含まれる倍音成分によって決まります。たとえば、バイオリンとフルートが同じ音程を出しても、聞こえ方が違うのは音色が違うからです。
この3つの性質を理解することで、音声信号処理の目的や手法がより明確になります。次のセクションでは、これらの音を人間の耳がどうやって感じ取っているのか、聴覚のしくみを見ていきましょう。
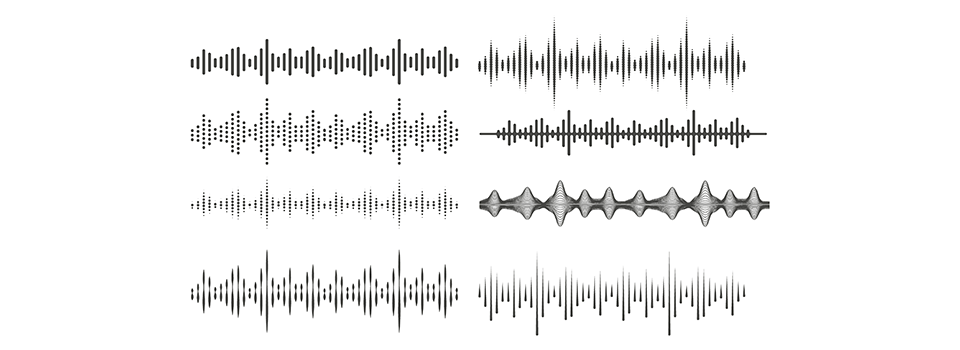
音波が“音”になるまで—耳のしくみをやさしく解説
音は空気の中を伝わる波ですが、それだけでは「聞こえる」ことにはなりません。私たちが音を感じるのは、耳というセンサーが音波を受け取り、脳に伝えているからです。
耳のしくみは、大きく3つのパートに分かれています。
① 外耳(がいじ)
空気中を伝わってきた音波を集める部分です。耳の穴(耳道)を通って、音波は鼓膜に届きます。
② 中耳(ちゅうじ)
鼓膜が音波の振動を受けて揺れると、その動きが耳小骨(じしょうこつ)という小さな骨に伝わります。この骨がてこのように働き、振動を内耳へと効率よく伝えます。
③ 内耳(ないじ)
振動は蝸牛(かぎゅう)という液体の入った器官に届きます。蝸牛の中には有毛細胞というセンサーがあり、振動を電気信号に変えて聴神経を通じて脳へ送ります。脳がこの信号を「音」として認識することで、私たちは音を“聞いている”のです。
※ちなみに、人間の耳は一般的に 20Hz ~ 20,000Hz (20kHz) までの周波数を感じ取ることができます。
この範囲を「可聴域」と呼び、年齢や環境によって変化することもあります。
このように、音波が耳に届いてから「音」として感じるまでには、物理的な振動 → 機械的な伝達 → 電気信号 → 脳の認識という流れがあります。このしくみを知っておくことで、音声信号処理が「何を模倣しようとしているのか」が見えてきます。
次のセクションでは、こうした音の理解がどのように音声処理技術につながっていくのかを見ていきましょう。
音を知ると、音声処理が見えてくる
ここまで見てきたように、音とは空気の振動であり、人間はそれを「高さ」「大きさ」「音色」として感じ取っています。そして耳は、音波を電気信号に変えて脳に伝えるしくみを持っています。
この一連の流れは、実は音声信号処理の基本的な考え方とよく似ています。マイクで音を拾い、デジタル信号に変換し、必要な処理を加えてスピーカーやアプリに出力する——このプロセスは、人間の聴覚のしくみを模倣しているとも言えます。音の周波数や振幅、波形の違いを理解していれば、「どんな処理が必要か」「どこを強調すべきか」「何を除去すべきか」といった判断がしやすくなります。たとえば、ノイズ除去や音声強調、エコーキャンセルなどの処理は、音の性質や人間の聴覚特性を前提に設計されています。
関連情報
音声処理の開発に役立つ DSP Concepts 社のオーディオ開発プラットホーム「Audio Weaver」をご紹介します。
お問い合わせ
本記事についてご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。
DSP Concepts メーカー情報 Top へ
DSP Concepts メーカー情報 Top ページへ戻りたい方は、以下をクリックください。
