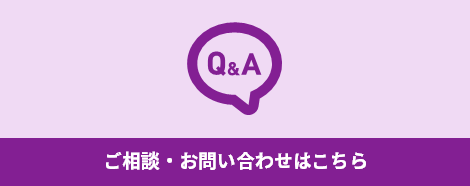2024年3月21日にオンラインセミナー「初心者のためのRS-232/422/485 回路設計基礎セミナー」を開催しました。
本セミナーでは、RS-232/422/485通信における伝送距離確保やデータ通信品質担保に向けた設計基礎として、各規格で発生しやすいノイズや反射などの電気的特性について解説しました。初めて回路設計に携わる方にも分かりやすいように、当日は以下のアジェンダで進めました。
【アジェンダ】
1. RS-232/422/485 規格概要(ノイズに強い/弱い、長距離伝送向き/不向きなど)
2. RS-232/422/485 接続例と利用用途
3. RS-232/422/485 設計時の注意点
- 終端抵抗が必要な理由
- フェイルセーフ回路
セミナーでは多くの質問をいただきました。その中からお客様からよくいただく質問を厳選し回答を紹介します。
紹介する質問の分類について
以下の5つのカテゴリーに分類して紹介します。
(1) 規格について
RS規格自体についての質問
(2) 周辺の回路設計について
周辺の回路設計時に気になるポイントなど
(3) ケーブル/コネクターについて
使用するケーブルコネクターなどの周辺機器に関する質問
(4) デバイスについて
RS規格のデバイスについての質問
(5) 使用上の注意点について
RS規格を使用するうえでの注意点
(1) 規格について
RS-232/422/485はプロトコルではないのでしょうか。
RS-232CはUART(Universal Asynchronous Receiver Transmitter)調歩同期式シリアル通信を使用し、RTS、CTSなどの状態信号を参照してフロー制御をおこないます。RS-422/485は電気的仕様のみを規定しています。
一般的にはUARTを使用しますが、規格と指定されているわけではありません。
RS-232Cドライバーとマイコン間をシリアル通信する場合の通信方式(UART、I2C、SCI など)を教えてください。
基本的にUARTで通信します。RS-232Cの通信がUARTを使って通信をおこなっているためです。
外部サイトですが、下記 URL先の図7付近にUARTの説明がありますのでご参照ください。
RS-232CドライバーのCとは何を指しているのでしょうか。当該部品の機能の概要を教えてください。また、RS-232の需要は現在もあるという理解で問題ないでしょうか。
CはRS-232 version”C”のCを意味しています。RS-232のversion Cが非常に有名だったため広く普及しました。
主に産業用分野においてPCとモニター/プリンターの接続をおこなう際に使用されることがあります。
EthernetやUSBに置き換えられ使用されなくなった環境を除き、古くから安定して動作し続けているRS-232も使用されています。
RS-485通信は64のノードが可能というのはどういう事なのか教えてください。32までの接続と認識していました。
規格では32ノードです。
RS-485の入力ピンに約15kΩの抵抗があるとします。この場合、この抵抗に流れる電流を1unit loadと呼びます。通常はRS-485ドライバーICは最大32unit load駆動するよう設計されています。しかし、レシーバーの設計を改善することで負荷電流を1/2に削減できるデバイスがリリースされました。このようなデバイスであれば32unit loadの2倍、つまり64ノードのレシーバーを接続することができます。
下記アプリケーションノートの表1をご参照ください。
各規格の電気的仕様の詳細を教えください。また、同一規格に準拠のICであれば、IC型番やメーカーを問わず互換性があると考えていいですか。注意するポイントがあれば教えてください。
RS-232/422/485はITU(The International Telecommunication Union)がそれぞれITU232/422/485という名前で規格化しており、以下より入手できます。
RS-422/485の仕様につきましては、下記の簡易版ドキュメントをご参照ください。
RS-422/485の規格を満たす限り、メーカーを問わず接続ができます。実績の豊富なTI製品の使用が安心です。
RS-232からRS-422への信号変換は容易にできますでしょうか?
可能ですが、シングルエンドとディファレンシャルの切り替えをおこなう必要があるので困難かと思います。シングルエンドの信号をディファレンシャルに変換するICが必要になります。また、コネクター形状も変わりますので変換アダプターが必要になります。
(2) 周辺の回路設計について
RS-485の終端位置は、複数対複数接続の場合どこに配置するのが最適でしょうか。
一般的には信号線の終点にあたる機器の前段に配置します。
伝送路の途中の経路で分岐している機器に終端抵抗を接続してもマスター側から発生する電気信号が反射波としてマスター側に戻ってきてしまい、適切な通信ができなくなる可能性があります。
伝送路全体のインピーダンスを特性インピーダンスに合わせこみ、信号の反射を最小限に抑えるために伝送路全体で始まりと終わりの2つ配置することを推奨します。
RS-485の半二重ではマルチドロップなので最終端に終端抵抗を入れても途中の経路で分岐しているので反射は起きるのではないでしょうか。
起きてしまう可能性もあります。
伝送路が長くなる場合や複数の機器が接続される場合に、中間にも終端抵抗を配置することが必要な場合がありますが、中間の経路にも終端抵抗を配置してしまうと伝送路全体のインピーダンスが変化し信号の反射が起きてしまう可能性があります。そのため、一般的には最初と最後の機器にのみ配置します。
機器やケーブルなどの仕様にあわせて、終端抵抗の値や配置する箇所を適切に調整することが重要です。
通信ICの送受信線の消費電流はどのように求めるのでしょうか。
バスに流れる電流として回答します。接続される構成によります。
RS-485の場合は終端抵抗が両端に必要ですので、並列接続された2個の100Ω 差動終端に、規定された1.5~5V範囲の差動振幅電圧発生させる電流が流れます。
終端抵抗の値を100Ωとすると、I = V / R ですので、ドライバーから流れ出る電流値{(1.5~5V)/50Ω}+各unit loadの電流×ポート数となります。
フェイルセーフ回路は各レシーバーに必要になるのでしょうか。
基本的に各レシーバーには必要ありません。フェイルセーフ回路は終端抵抗と併せて実装します。そのため各レシーバーではなく、終端抵抗近くのレシーバーに実装してください。
ケーブルの断線がどこで発生したかを確認したい場合は、複数のレシーバーにフェイルセーフ回路を追加してもよいと考えます。
ケーブルの中央あたりで断線した場合、断線箇所以降のレシーバーがすべて論理HighかLowになります。
反対に断線前のレシーバーは受信ができている状態になります。この状態の違いを確認する事で断線箇所を把握することが可能かと思います。
注意点としては、抵抗が増える事により信号が減衰したり、ドライバーの出力電流が余計に必要になります。
RS-485の終端抵抗がケーブルのインピーダンスに合わせるのが良いとされていますが、ケーブルインピーダンスと終端抵抗の差がどの程度離れると反射が起きてくるでしょうか。
反射程度は反射係数にて計算をおこなうことが可能です。本セミナーの以下FAQをご確認ください。
「フェイルセーフ」とはフローティングで通信ICの「誤動作防止」とのことですが、故障防止のことでしょうか。
誤動作防止を目的としております。ただし、フェイルセーフ対策をおこなわなかったため、ICの出力論理が確定せず出力後段のICが誤動作をおこしシステム全体としての故障に繋がる可能性もあります。故障防止にはサージ保護回路や絶縁での対策を実施してください。
コスト、面積の問題がなければ、Idle、Open、Shortに対応した右側のフェイルセーフの方がよいという認識でよいでしょうか。
ご認識の通りです。右側のフェイルセーフ回路はShortにも対応した回路であり、より堅牢性が必要な場合はご検討いただくのがよいかと思います。
また面積に制限がある場合は、フェイルセーフ対応のIC(THVD2410/50など)をご使用ください。
(3) ケーブル/コネクターについて
それぞれの通信方式についてどのようなケーブルを用いることが好ましいでしょうか?また、シールド付きの物を用いる場合のシールド処理の方法についても教えてください。
それぞれの通信規格によって使用されるケーブルが異なりますが、一般的に使用されるケーブルを紹介します。
RS-232の場合、複数の単線ワイヤーを1本にまとめたケーブルを使用します。
RS-422/485の場合、複数の100Ω差動ワイヤーを1本にまとめたケーブルを使用します。産業向けとしてはシールド付きのケーブルを使用することが一般的です。
シールドの処理方法について
シールドのGNDはフレームGNDに接続し、基板内のGNDとは分離します。基板の中に電流が流れないように処置することでEMI低減ができます。下記アプリケーションノートのFigure 27を参照ください。
通信ケーブルの特性インピーダンスとはどういったものでしょうか。
通信ケーブルの特性インピーダンスとは伝送線路に交流信号が通ったときに発生する電圧と電流の比です。
電線の太さや感覚、絶縁体の誘電率によって決まります。以下の計算式で算出できます。
【計算式】
Zo(特性インピーダンス) = V(電圧) / I(電流) = √⊿L / ⊿C
⊿L:伝送線路の単位長さあたりのインダクタンス
⊿C:伝送線路の単位長さあたりの容量
終端抵抗はケーブルの特性インピーダンスに依存するとの事ですが、一般的にRS-422やRS-485で使用されることが多いケーブルの特性インピーダンスはどれになりますでしょうか?
100Ωや120Ωの特性インピーダンスを有したケーブルが多いと認識しています。
RS-422、RS-485で用いる通信ケーブルはツイストペアケーブルが推奨されますか?
ツイストペアケーブルが推奨となります。RS-422、485は差動信号で通信をおこなうため、ツイストペアケーブルを使うことにより外来ノイズの影響を受けにくくし、外部に対するノイズの影響を抑える事ができます。市場に流通しているケーブルはツイストペアケーブルが多いです。
RS-422、RS-485でよく使われているコネクターはありますか? ターミナルブロックと、D-SUBコネクターについてはよく見かけるのですが、RJ45などはいかがでしょうか?
RJ45コネクターが使用されるケースもあり、D-SUB、RJ45がよく使用されるコネクターと思います。
次いでターミナルブロックも使用されている認識です。
RS-485の接続時に一般的なコネクター、端子台などはあるのでしょうか。
一般的には、D-SUBコネクターやRJ45コネクター、ターミナルブロックが使用されます。
(4) デバイスについて
35pのTHVD1424/54には最大通信速度が20mbpsとのことでしたが、最大は10mbpsではないのでしょうか。
RS-485を使用したアプリケーションのほとんどが10Mbpsよりも低い速度での動作を想定したものになっておりますが、10Mbps以上での通信が可能な場合もあります。
そのため、THVD1424/54のように最大通信速度が20Mbpsと記載されるICもあります。この速度は、ICの推奨動作条件がすべて揃い、ANSI/TIA/EIA-485-A規格の条件に完全に準拠した場合に実現可能となります。
THVD2410/50を使用すれば、直列抵抗やプルアップ/ダウン抵抗が不要になるということでしょうか。
ご認識のとおりです。THVD2410Vの話になりますが、不定の値が入力された際にHighの信号を出力するタイマー方式の回路が内蔵されています。
例えば、ショート状態になり入力信号が0Vになった時、出力はHighを出します。そして、入力信号がVTH_FSHの電圧範囲を超えるまで、Highを出力し続けます。
例としてISO1430Bを使用する際、絶縁側のVcc2が5Vである場合、通信ラインの作動信号は何Vになりますでしょうか。
コモンモード電圧は1~3V、Typ Vcc2/2となり、差動振幅2.1V Min、Typ 3.7V になります。
(5) 使用上の注意点について
サージ保護ダイオード内蔵のICは、発熱に対して通常のICよりも特別なケアが必要になるのでしょうか。
サージ保護ダイオードに生じる発熱は瞬時なので外部での対策ができません。
サージ保護ダイオードのサイズを大きくし、熱容量を大きくするなど、IC設計上の対策で対処します。
外付けのサージ保護ダイオードの発熱の対策例をご教示お願いします。また、IC内蔵タイプはダイオード発熱への対策もお願いします。
外付けダイオードの発熱対策としては、放熱フィンを設ける方法があります。
絶縁することによるデメリットはありますか?
デメリットとしては、価格と実装面積の増加があります。
・価格
絶縁ICは通常のICよりも高価であり、トータルの部品点数が増えるため、総合的な価格が高くなります。
・面積
絶縁ICは沿面距離を確保するためにパッケージサイズが大きいケースがあります。
また複数の部品を使用して絶縁を実現させる場合、必要な部品が増えますので実装面積が増えます。
RS-485において通信の衝突を回避する方法を教えてください。
ソフトウェア制御によるバス制御の方法があります。
ソフトウェア制御では、送信データを送信線に載せる前に、送信線の電圧レベルをソフトウェアで制御することで送信と受信の間での衝突を防止します。
RS-485は活線挿抜可能でしょうか?その場合、終端を配置する場所はどこが良いですか?
RS-485は活線挿抜を認めておりません。ですが、RS-485の対策としましては、過渡過電圧保護の項目で説明したサージ保護ダイオードを追加して過電圧からICを保護する方法があります。
ICのFault Protection電圧内であれば、保護回路の追加は不要ですが、活線挿抜の可能性がある場合は安全のためにもサージ保護回路を追加するのがよいと思います。他社様の記事になりますが、下記URLの内容が参考になります。
また、終端抵抗は最終端のレシーバー前段に配置します。
セミナーを振り返りたい方にはオンデマンド動画もあります。
質疑応答の一部を厳選しご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。セミナー本編はオンデマンド動画も準備しています。
以下より簡単な登録をしていただくことでオンデマンド動画の閲覧が可能となりますので、ぜひご登録ください。
お問い合わせ
不明点があればお気軽に以下よりお問い合わせください。