老舗フィルムメーカーが挑む!
課題解決と事業変革を実現するDXの第一歩
──四国化工株式会社様
安全性やサステナビリティを追求した、医療・食品包装のフィルム製造などを手がける四国化工株式会社。数十年にわたる歴史をもつ同社は、経営企画室の室長である中西氏を中心に、DXやAIの活用による業務改革を推進しています。その取り組みの詳細について、お話を伺いました。
本インタビューの参加メンバー
四国化工株式会社の方々
- 経営企画室 室長 中西 観大様
- 技術開発部 技術開発課 課長 松浦 亮様
株式会社マクニカ
- イノベーション戦略事業本部 デジタル事業開発部 共創オファリング課 村澤 佑磨
- イノベーション戦略事業本部 デジタル事業開発部 プロダクト企画開発課 山田 大樹
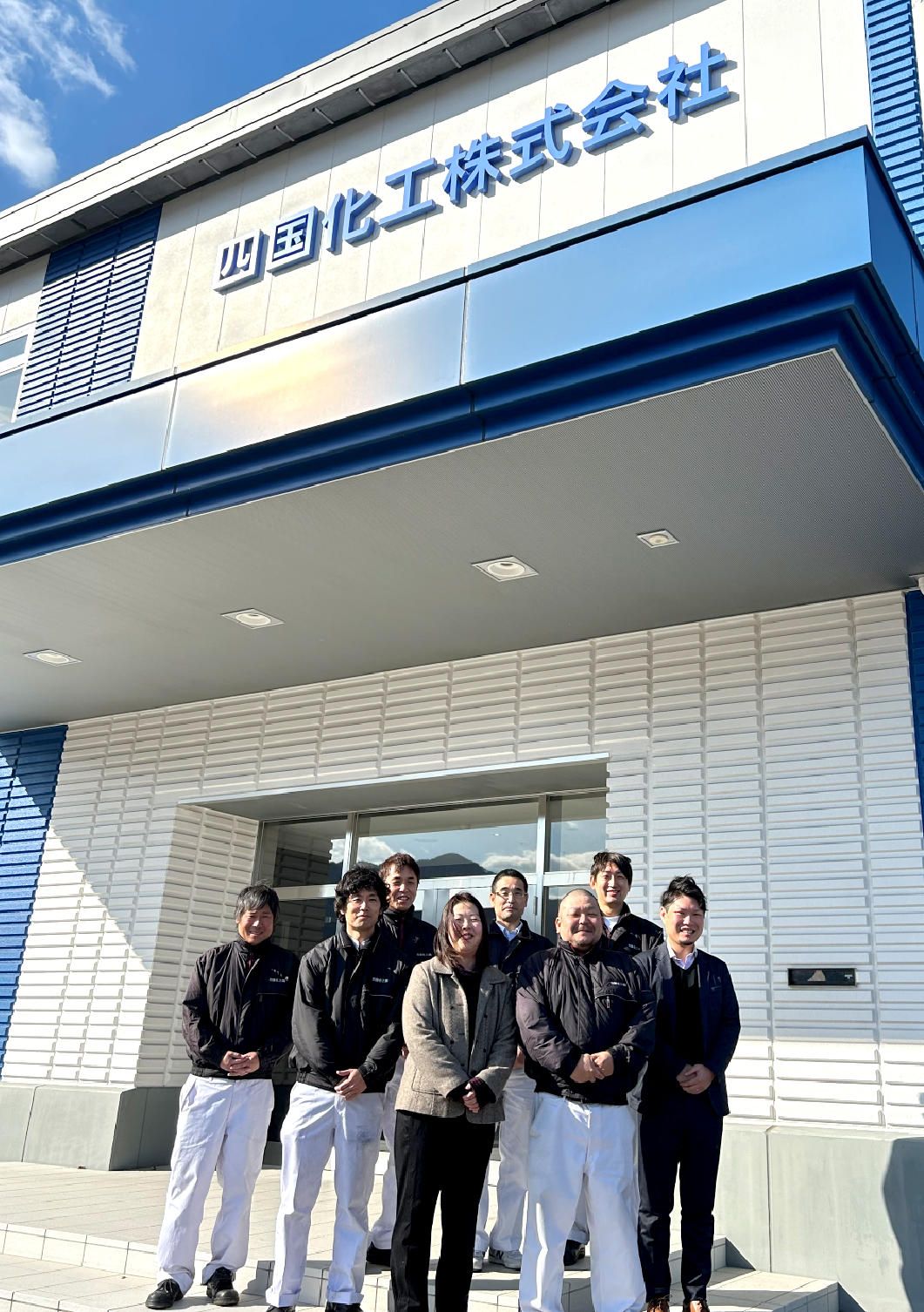
- 課題
-
- 「DX」の言葉だけが先行
- 人口減少にともなう人材確保の難しさ
- 「課題に気づけない」現状
- 目的
-
- 製造業以外の武器を得る
- 危機感を持った組織改革
- 人への投資による、市場優位性の確保
- 効果
-
- 出会いが生んだプロジェクトのはじまり
- 生成AIの業務活用イメージがわいた
- 「アナログからデジタルへの変換」にも期待
メーカーが抱える、切実な課題の数々
昭和58年創業の老舗フィルムメーカー
中西様:四国化工株式会社は香川県の東かがわ市に本社を置くフィルムメーカーで、前身である白鳥化工から事業を受け継ぎました。設立は昭和58年(1983年)で、2024年で創業42年目になります。
松浦様:食品・電子・医療と幅広い分野に進出していますが、あまり生活のなかでは見ない商品がメインです。食品や電子では消費者の目に留まるようなものではなく、業務用や工場間の輸送に使われる包装資材をメインに扱っています。医療分野では、点滴の輸液バッグなどが当てはまります。最近では、Amazon(EC)でのB to Cでの販売にも参入しています。

DX推進が必要になった背景
中西様:DX・IT・IoTといった言葉は数年前から社内でも使われていましたが、言葉だけがひとり歩きしている状態でした。たとえば、中期の経営計画にも「DXをします」と書かれてはいるものの、それはごく一部のプロジェクトに限られていました。それでは社員に根づきませんし、取り組んでも大きな効果は期待できません。
松浦様:四国は全国平均よりも早く過疎化が進んでおり、今後も労働人口の大幅な減少が懸念されています。東かがわ市の人口は現在(2024年11月時点)で27,000人ほどですが、20年後にはさらに約4割が減り、17,000人ほどになるのは間違いないだろうと言われています。東かがわ市については、「消滅可能性自治体」についても示唆されています。今以上に厳しい状況を迎えることが想像できます。
中西様:私たちの会社は、そうした地域にあります。弊社の社員は約260名で、7割ほどが製造部門に従事していますが、部署単位では平均年齢が50歳を超える部門も少なくありません。そうなると10年後には人材不足になり、おそらく業務を回せなくなるでしょう。高校卒業後に就職するという方もほとんどいらっしゃいませんし、業務によっては交代勤務のシフトもあるので、大学の新卒を含めても採用はかなり厳しいのが実情です。
事業の継続が危ぶまれる状況ですが、製造業は弊社メインの事業体なので、「やめます」と言ってやめられるものでもありません。人手不足と製造業への高依存、この2つが大きなネックとなっているわけです。しかし、現時点で弊社は、経営的に東かがわ市を離れることは想定していません。
課題を見つけられない状態
中西様:ITやデジタルという言葉が、業務のなかでつながっていないことも課題だと感じています。自身の業務に結びつけるとなればなおさらで、そもそも自身の日々の業務がルーティンワークであることを認識できていないこともありますし、私もふとした瞬間にハッと気づいたりします。こうした状態では、課題を見つけられないことが問題です。
弊社の業務にはアナログなプロセスが非常に多くありますが、世の中では徹頭徹尾、デジタルで事が進んでいます。そんな状況で業務の一部分だけを効率アップして「DXしています」と自己満足しても何も変わりませんし、競合にも遅れをとってしまいます。だからこそ、社内では「私たちはまだビジネスをしていない、だから準備をしましょう」と伝えています。
邂逅がプロジェクト発足の起点に
製造業も含む多様な実績を評価
中西様:私は経営にはビジョンと覚悟がもっとも大切だと考えています。そこで、2024年に経営企画室が立ち上がり、本格的なDX推進に着手し始めました。
松浦様:社員のDXやITに対するリテラシーを高めるのも一筋縄ではいきませんし、弊社が単独でそれを実現させるのは困難だと感じていました。
中西様:いろいろなコンサル会社にコンタクトを取るなかで出会ったのがマクニカ様です。弊社は今後、製造業以外の新規事業も立ち上げたいと考えているのですが、マクニカ様はさまざまな分野での実績をおもちですし、やりたいことを具体化する力もあり、強力にサポートしていただけると確信しました。
松浦様:今回のプロジェクトが立ち上がったのは、マクニカ様との出会いがあったからと言っても過言ではありません。
「生成AI勉強会」に参加してみて
中西様:私は普段から生成AIを活用しており、「便利だからみんなにも使ってほしい」と思っています。なにより、生成AIを活用することで新入社員でもベテランでも業務のクオリティをある程度平準化できるのは、大きなメリットです。社内で使える環境を整えていきたいと思っていた矢先に、村澤様から勉強会をご案内いただけたのは幸運でした。今回は取締役から管理職までを対象としましたが、今後は係長など、より対象を広げていきます。
勉強会はとても楽しかったですね。現場では議事録や日報作成に役立つ「おまとめ忍者」も使わせていただきました。こういったツールがあることは知っていましたが、実際に使うと便利ということを社内で体験・共有できてよかったです。たとえば、私たちが普段使っている用語の割合をデータ化すれば、いろいろなことが検証できるはずです。私が常に考えていた「アナログからデジタルへの変換をいかに進めるか?」に対する答えや、その必要性を改めて知ることができたと思います。

ビジネスの整理は継続して実施
中西様:ただ、製造サイドに関する大規模なDX化の依頼はまだ先になると考えています。なぜなら、私たちが「残すビジネス」と「残さないビジネス」をまだ整理できていないからです。この先10年、まだ収益が期待できるものを精査し、DX化する設備などを見定めておかなければなりません。
松浦様:設備は資本さえあれば導入できますし、導入さえすれば類似製品を製造することもできます。製造技術を組み合わせれば付加価値は付与できますが、DXやAIが進化してくると製造技術は平準化されて、差別化が図り難くなります。
中西様:現状は「日本製で、商談も日本語でできる」という理由で買ってくださるお客様もいらっしゃいますが、同等のスペックの設備は海外にもありますし、いずれは「日本だから」という特権も失われるでしょう。仮に、特定の設備を弊社だけが持っていれば市場で勝てる可能性はありますが、逆に弊社しか作れないとなると、BCPの観点からご使用できないお客様も出てくるはずです。このあたりは、塩梅が非常に難しいところですね。
ステークホルダーへの積極的なアプローチ
DX実現に向けての打ち手
中西様:私は今後20年スパンで予想される労働人口の減少などのデータも交えたうえで、DXの必要性を社内で説明しています。昨年には「既存ビジネスの変革」について議論し、その課題に対する各自の考えをまとめました。
結果、私と周囲では認識や想定しているスピード感に大きな乖離があることが分かりました。課題解決には長い時間と労力が必要だと思っているのは、解決の手段を知らないことが要因です。私はまず優先度を決めることが重要だと感じつつ、「現状のアナログなプロセスではなく、デジタルなプロセスで課題へアプローチして欲しい」と伝えております。
松浦様:一方で、ものづくりのプロセスにおいては、現状フィルムを製造して袋にする工程は機械1台に対して社員が1人必要なので、そうした人材は引き続き必要です。「自動化すればよいのでは?」という声もありますが、製袋機1台をフルオートメーション化するのには相応のコストがかかるので、なかなか難しい話です。従来の製袋機の購入費と人件費とを合わせた金額を比較すると、大きな差があります。
それにオートメーション化すると生産量を確保しなければなりませんが、需要は上下しますし、10年後には人口減少に伴い内需がさらに縮小します。仮に何十台もの製袋機すべてをオートメーション化すると莫大な費用がかかるのに対し、販売量が落ちるなかで投資したコストを回収するのは現実的ではありません。
中西様:私たちを含む地方の中小企業がいますべきは「大量生産に舵をきること」ではなく、「人とITで稼げるように、生産設備よりも人と人が育つ環境に投資すること」だと思います。
7つのプロジェクトで改革
中西様:こうした状況があるなかで、まずはDX化のロードマップを進めることの優先度が高いと思っています。今後、DX推進、商品企画、商品開発などクリエイティブな人材がさらに必要です。社員がリスキリングできるように、継続的に成長できる環境を整備する必要もあると考えています。
現在、ビジネスの変革を行うために7つのプロジェクトを進行させています。内容としては「既存事業の変革」「再生事業の推進」「RPA導入」「B2C事業の立ち上げ」「原価精度向上」「フィルムの薄膜化」「DX推進」です。
これらすべてのプロジェクトを進めるにあたり、特にプロジェクトメンバーに必要なマインドが、アントレプレナーシップだと考えています。失敗を恐れず常にチャレンジャーとして挑戦し、イノベーションを起こせると信じて日々の仕事を前向きに進めることが大切です。また、我々のプロダクトに対してお客様が最大限のバリューを感じてもらえるように、常にUXを意識した商品企画や商品開発などを心掛けたいと思っています。
松浦様:すべてのプロジェクトを直近1年程で立ち上げ、社内に変革の意識が芽吹いたとはいえ、まだ根付いているとはいえません。やはり、今までのやり方を変えることに抵抗がある社員はいます。しかし、世の中は恐ろしいスピードで変化しており、私たちの想像をはるかに超えていきます。既存のビジネスはすでにコモディティー化しているものも多く、現実を正しく受け止める必要があります。

中西様:多くの人は「変化する」ことを恐れ、リスクを過大評価する傾向があります。リスクヘッジの方法を知らないがために妄想して、自分のなかでリスクを膨らませてしまう傾向にあります。だからこそ、私は「リスクはヘッジできればリスクではない」と言い続けてきました。存在するリスクをどのように減らすかを考え、実際にアプローチしてみることこそが大切だと思います。
なにより、人生を楽しんでほしい
目標のその先
中西様:「自分じゃないほうが良い」と思った瞬間、私の役目は変化し、新しいゴールを新たに設定すると思います。四国化工については、おそらく四国で一番になりたいというレベルでは、今後生き残っていくことは難しいと思います。当面の目標はそれとしても、その先では日本や世界を見据えるビジョンが必要だと思います。
覚悟があればなんでもできます。大切なのはどこに軸を置くかです。東かがわ市でビジネスを続ける覚悟があるなら、それに応じたビジネスをしなければなりません。
松浦様:自社の状況と世相から、自主的にビジョンを描ける人材が生まれてくるのがひとつのゴールだと思うので、まずはそこを目指して、四国化工の風土や労働環境を整えるためにDX化をマクニカ様とともに進めていきたいと考えています。

中西様:「強い個体を得るには、遠縁の遺伝子同士を交配させて、補完的な要素を持たせるのが良い」と言う説を聞いたことがあります。これはイノベーションを起こそうとするときも同様で、私たちの場合はフィルム業界ではないところからノウハウを得るのが良いと考えています。DXやAIは、もっとも手っ取り早くそれを実現する手段と捉えています。
とはいえ、導入した時点でそれらは過去となり、いずれ当たり前になってしまうので、次の手を考えておかなければなりません。重要なのはAIと四国化工となにをかけあわせるか?ですが、我々は情報や経験も含めていろいろなものを感じ、学ぶことで何かを見つけられると確信しています。
我々はこのAI時代を乗り越えるために、覚悟を以って決断を行い行動することがもっとも重要です。四国化工の社員には「素直に」「学び」「恐れず」、そしてなにより、人生を楽しんでほしいです。

四国化工株式会社
- 事業内容
- 医療・食品・電子・工業用フィルムの開発・製造・販売
- 創業
- 1983年(昭和58年)4月11日
- 従業員数
- 263名
- ウェブサイト
- https://www.shikoku-kakoh.com/company/
\Re:Alizeの詳細はこちら/
