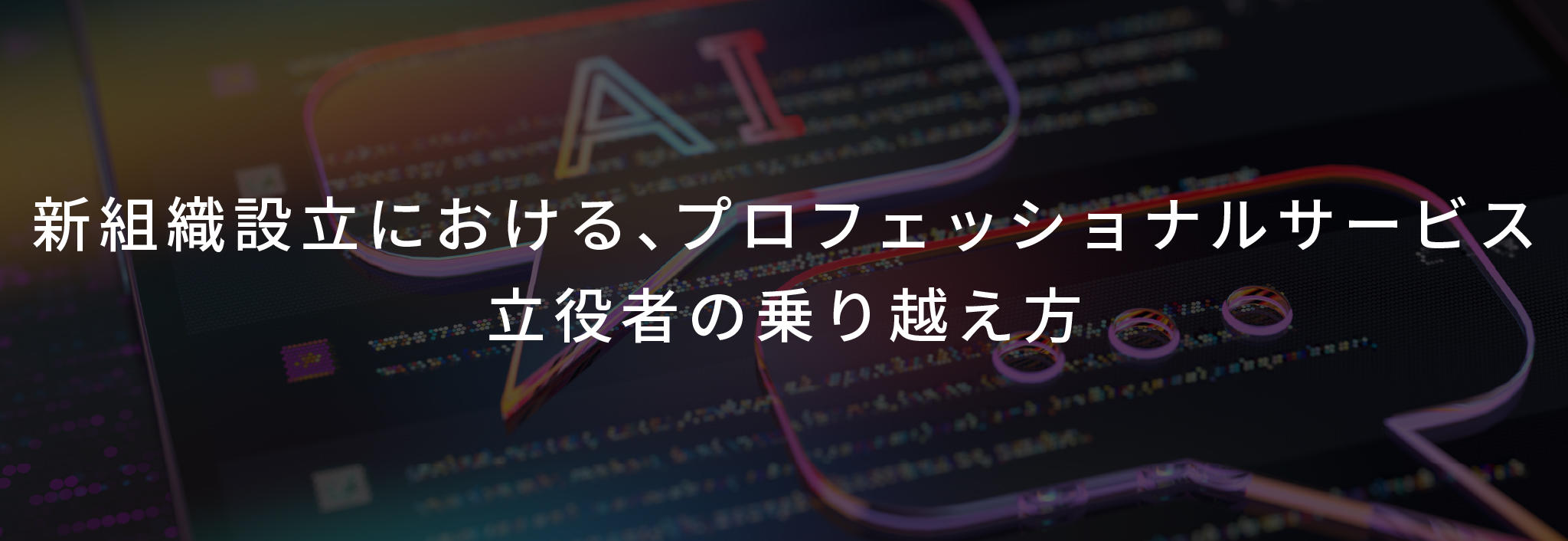
最先端テクノロジーを駆使してさまざまな事業を展開しているマクニカには、AI技術を活かした製品・サービスの開発や提供をおこなう「デジタル事業開発部」が存在します。
同部署は「スピード感と柔軟性、とにもかくにも“まずつくる!”のマインドで、時代の変化を恐れずに挑戦と変革を続ける」というポリシーを掲げ、激変する市場の荒波にも負けず、日々進化しています。
そのさなか、2024年に新たに誕生したのが、Re:Alize Professional Service(以下、RPS)という独自のサービスです。今回はそのチームをけん引する小林 俊介(こばやし しゅんすけ)と、メンバーである村澤 佑磨(むらさわ ゆうま)に、RPSの生い立ちや組織の目指す方向性などを訊きました。
📌この記事のポイント
新組織の立ち上げに必要な要素
→ビションの明確化/適切なチーム編成
成功事例から学ぶ、プロフェッショナルサービスの役割
→技術導入だけでなく、文化・仕組みの変革が重要
DX推進には「現場の理解」と「経営層のサポート」が不可欠
→小さく始め、すぐにフィードバックを得て調整する
PoC(概念実証)成功のカギは「仮説検証のスピード」
→知見を活用し、課題を最速で解決するアプローチ
組織の構造化で「強み」を明確に
――まず、RPSについて教えてください。
小林:RPSは、AI技術をコアとしてお客様におけるDX推進を具体的にメニュー化し、「プロフェッショナル」の名にふさわしい高度な知的生産を実現するサービスです。
私たちが所属するデジタル事業開発部では、「新たな価値を創造するための共創基盤」である「Re:Alize」というサービスが3年ほど前に誕生しました。いわばRPSの母体です。Re:Alizeは当初、AIのPoC提供を中心に事業を展開しており、一定の売上を達成していました。しかし、市場の成熟に伴い、新たな方向性が求められるようになりました。
そこで、次はIoTを組み込んだデータ取得や、AIモデルなどのシステム開発やデリバリーをおこなうことになりました。しかし、AIの実装だけではお客様の期待値を十分に満たせないことが徐々に分かってきました。この領域は、明確に要件を定めて開発を行うことが非常に難しいからです。いろいろと模索するうち、「AI開発には従来と異なるアジャイルな手法・クイックな企画作成と仮説検証・ステークホルダーの巻き込みなどが必要だ」と私たちは気づきました。
それらを学んでいくうちに、今度は「お客様の業務をAIで改善するだけでなく、いわゆる攻めのDXを目的とした、おまとめ忍者のような自社開発のシステムを外販すれば、新しいビジネスモデルを提供できる」ことが分かり、Re:Alizeはさらに活動範囲を広めることになりました。
特にここ4~5年は、AIが目覚ましいスピードで進化しています。Re:Alizeは常にその先端を追うべく変化を繰り返した結果、提供できるサービスが多様化してきたわけですが、「いろいろできます」を一言でお客様に伝えるのは困難です。また、今後ビジネスをスケールさせていくにあたって新しいメンバーが加わるとき、彼らをけん引するためにも明確な説明が必要になります。こうした背景からRe:Alizeを構造的に整理した結果、RPSがその一要素として確立しました。

――組織設計を進めるうえで、最初に取り組んだポイントは何ですか?
小林: 2つあり、1つ目は自分たちがデリバリーできるサービスの棚卸し、2つ目はストーリーの整理です。前述のとおり私たちは大きな変化を遂げながら、いろいろなサービスを提供してきました。しかし、そのときどきで違うことをやっていそうでも、じつは「AI技術をコアにお客様のDXを支援する」という1つのストーリーが常にあって、それがRe:Alizeの誕生から変わってないことの可視化が重要だったと思っています。
――どんなところが大変でしたか?
小林:棚卸しは実績を見直すだけなのでさほど大変ではなかったのですが、ストーリーの整理には苦労しました。お客様の要望を聞いたときはその場に必要な対応をすればよいですが、「なぜあのときは、ああいった案件が多かったのか?」「なぜ翌年は、ああいった案件が増えたのか?」といった市場変化の分析を後からおこない、説得力のあるかたちにまとめるのが非常に難しかったですね。
――それをどう乗り越えたのですか?
小林:とにかく本をたくさん読みました(笑)。フレームに落とし込むための方法を知るには、先人の知恵を借りるのが最適だろうと。「プロフェッショナルサービスのビジネスモデル」と「プロフェッショナル・サービス・ファームの生存戦略」の2冊を特に活用しましたが、いずれも非常に役立ちました。
村澤: 「乗り越える」という観点では、スキルやノウハウのある中途社員の採用も一要素にあると思います。Re:Alize全体だと、以前はAIベンダーなどで活躍していた人材が、私も含め何人か直近で採用されました。マクニカはいずれ非常に強力なケイパビリティを確立できると私は感じているのですが、そこに到達するにあたっては、未踏の領域に挑戦した経験のあるメンバーの有無が成否を大きく分けます。AIに詳しい人材の採用も一筋縄ではいきませんが、数が集まってくるとよいですね。

少リソースで業務を回す秘訣は「ボトムアップ」にあり
――RPSのチームメンバーを選ぶ際には、どんなスキルや資質を重視しましたか?
小林:新規事業開発におけるビジネス的な知見・AIのプロジェクトマネジメント経験があることはもちろん、文化や思想が私たちと合っていて、柔軟性があるかどうかを重視しました。ポジティブな対応・クイックな仮説検証が求められる私たちのビジネスでは、挑戦心と前向きな姿勢が求められます。
デジタル事業開発部の部長や私がもっていなかった、顧客管理の経験も重要ですね。従来はAIという言葉をフックにすれば売上をたてられていましたが、今はもっと戦略的にやらなければスケールしないので、顧客行動の観察やデータ化に詳しい人材はやはり必要でした。
――RPSのチームは非常に精力的に活動をしていますが、それに対してメンバーは4人と少ないように思います。限られたリソースで運営するために、どんな工夫をしているのですか?
小林:私は「各自がやりたいことをでき、モチベーションを保てる環境を用意すれば、チームが最大限の力を発揮できる」という考えに基づき、1週間に2回ほど「人は自分のやりたいことしかやらない」と自身に説いています(笑)。何かを規制するのではなく、できる限りやりたいようにやってもらい、そこからのボトムアップを重視しています。
村澤:RPSはお客様によっていろいろなカスタムをしなければならないので、まだまだ内容や方向性がフワッとしています。そのため、今後は「武器」、つまり売り物の作り込みが大切です。これが完成すればマクニカ全体の営業リソースを活用でき、たとえば異なる部署の商談中であっても私たちの商材を紹介してもらえるようになります。その結果、営業工数が減るのは大きいですし、売り物ができればチームとして進むべき方向性も明確になります。

小林:ビジネス開発においては従来のコンサルティングビジネスから学ぶことが本当に多く、今後はRPSをスケールさせるためにサービスを型化していきたいですね。
課題解決に役立つ「文化人類学」と「地政学」
――活動のなかで困りごとが起きた場合はどのように解決していますか?
小林:やはり読書です。書籍そのものや内容をチームに共有することもありますが、積極的に説明したり、読むことを強制したりはしません。読書が本当に必要なタイミングは人それぞれですから。あとから興味がなかった書籍でも、ふとした瞬間に「これだ!」と気づくこともありますし。
読書をインプットとすると、その反対のアウトプットも大切にしています。私たちは情報を整理する際によくフレームワークを活用しており、その多くは書籍からそのまま引用しています。
ただ、RPSでAIビジネスを企画する際には一般的なAIベンダーが活用しているフレームではなく、グローバルな経営戦略に特化しているBCG(ボストン・コンサルティング・サービス)のフレームをお借りしました。なぜなら、私たちは課題を抽象的に捉えることが非常に重要だと考えているからです。

たとえばコンサルティングで経営層などのお客様にインタビューする場合は、インタビューのやり方・ヒアリング内容・インサイトのつかみ方などを考える必要があります。このときお客様が表面上で話していることではなく、本質的な部分にアプローチするために本当に役立ったのはインタビュー教本ではなく、文化人類学から生まれた「エスノグラフィ(※)」という根源的な手法でした。
※:民族学・文化人類学などで用いられる研究手法。調査対象の生活に身を置き、行動観察やインタビューを通じて習慣・価値観を分析する。
対企業のコンサルティングでは、お客様の文化に合った提案をしなければ当然うなずいてはもらえませんし、「大枠は理解したけどウチには合わない」などと言われてしまいます。また、お客様側の社長や数名のプロジェクトメンバーに対する1時間のインタビューで聞いた表面的な話だけでは、深く刺さる提案をすることは非常に難しいと思います。そこで私は、異文化を体系だてて整理する文化人類学に着目しました。
文化人類学の学者たちはかつて、見たことも聞いたこともない言語に触れながら、相手の行動を観察して理解したそうです。異文化、私たちでいうとお客様について知ることはもちろん、「なぜ相手がそうした行動をとるのか?」を理解するアプローチはコンサルティングや開発に役立つので、この領域に携わるかたは勉強しておいて損はないと思います。
また、ビジネスの企画には地政学も役に立ちます。ビジネス環境、特にAI市場は変化が激しいですが、少なくとも地球が地球であり続けるかぎり、普遍的なことは数年ではまず変わりません。たとえば日本は島国で中国やアメリカは大陸ですし、それぞれの位置関係も同じなので、大局的なビジネス構造は決まっています。そして、いろいろなビジネスがそこから生まれてくることも変わらない事実です。
他者を知る文化人類学や変わらないことを知る地政学をあらかじめ学んでおけば、きっと困ったときに対処を考える際の軸になってくれると思います。

――今後の目標を教えてください。
小林:私たちがもっとも力になれるであろうお客様のセグメントを特定することです。これまで10数年にわたって社会人として仕事をしてきましたが、業界だけでも数が多く区切りきれないので、本当に難しいことだと感じています。
この目標の実現に必要だと感じているのは、やはりインプットとアウトプットをスピーディに回すことです。ただ、現在はデジタル事業開発部の人が増えていて、その分ココミュニケーションが必要な機会も多くなっています。そうなると仮説検証のスピードは遅くなるし、理解のすれ違いなどのリスクも出てくるので、いかにそれを減らせるかが勝負だと思っています。
こうした課題を乗り越えた先で、特定の市場向けにズバッと刺さるサービスを開発していきたいですね。
