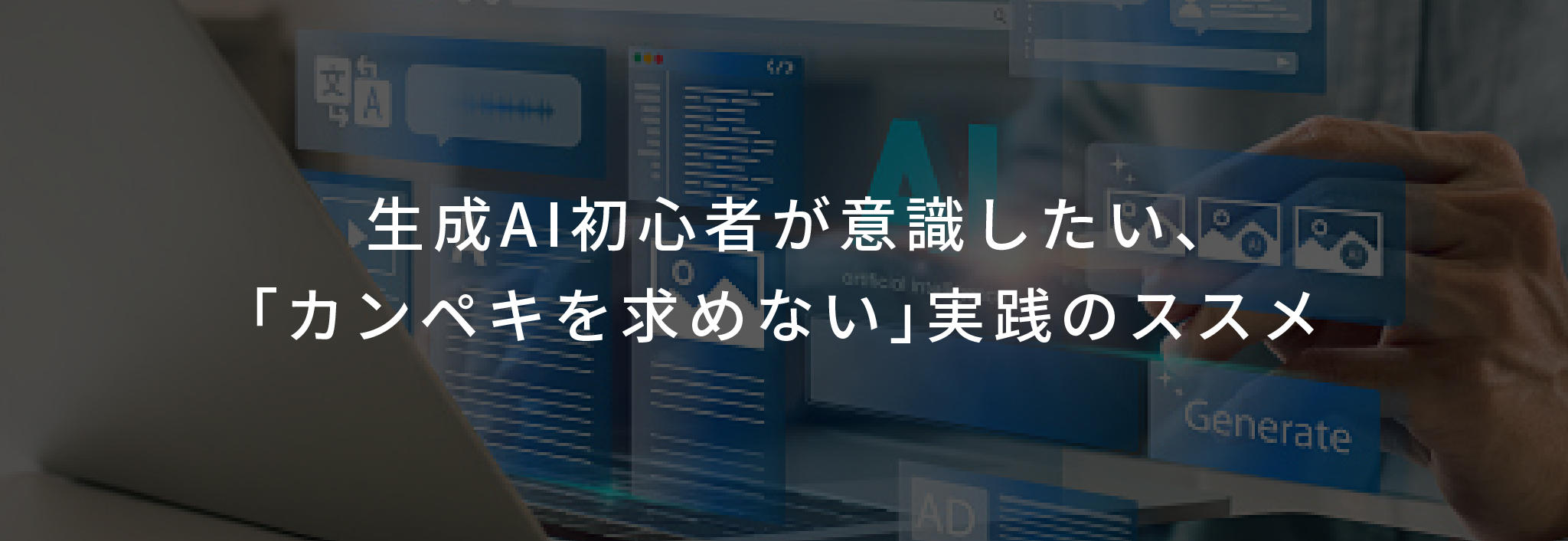
企画案出し・壁打ち・プログラミングなど、なにかと便利に使える生成AIですが、皆さんは日々の業務や生活などでどのくらい活用していますか? その存在は毎日のように目や耳にするものの、「実は自分で使うぶんにはあまり……」という方も少なくないかもしれません。
そこで本コラムでは「今後、ぜひ生成AIを活用してみたい」と願う方が知っておきたい、生成AI活用におけるメリットやポイントなどを解説します。“変革”という名の大海へ、いまこそ生成 AI に慣れ親しむためのオールを手にして漕ぎ出しましょう!
生成AI活用のメリット
めまぐるしいスピードで進歩を続け、幅広い用途に適応している生成AIは、うまく使いこなせば非常に頼もしい味方になってくれます。ほんの一例ではありますが、まずは生成AIの活用によって得られるメリットの一例を見てみましょう。
成果物の質が安定する
人に作業を依頼した場合、「AさんとBさんで成果物の中身が(依頼の内容しだいでは)まったく異なる」といったケースは往々にして起こるものです。たとえば、議事録などの文章を書くものや、Excelの加工などは人によって特徴(クセ)が出るかもしれません。
しかし、生成AIは基本的に命令文(プロンプト)の内容に基づいて処理をおこなうため、毎回100%同じとはいかないまでも、異なる2人の人間に任せたときほどは内容に違いが出にくいと考えられます。つまり、成果物の質が安定するということです。
さらに重要なのは「生成AIに命令するのがAさんでも、Bさんでも、Zさんでも、使う命令文の内容が同じであれば、結果を大きくブレさせずに同じ作業を繰り返せる」という点です。これは会社のような多くの人が働く場所において、極めて強力なメリットだと言えます。
スムーズな思考整理&「たなぼた」も?
生成AIが使い手のインプットに対して素早く回答してくれる利点は、自分の考えをスムーズに整理することに活かせます。ときには、自分では気づかなかった思わぬ発見があるかもしれません。
「人に相談すると時間をもらうことになるから気が引ける……」という場合でも、生成AIが相手なら気にする必要がなく、自分の好きなタイミングで実行できる点もナイスです。
客観的な意見をくれる第三者である
生成AIは良くも悪くも、基本的には使い手の背景を理解していません。これはすなわち、つねに客観的な意見をくれる存在であることを意味します。例として、同じ部署にいるメンバーの役割が偏っていて、ちょうどよい相談役がおらず有効な意見をもらえない(出しにくい)パターンでも生成AIなら気軽に相談できますし、その回答はたいていの場合、何らかの役に立つはずです。
最終的には人対人になるとしても、その過程の相談役として生成AIを活用してみることで、活路を見いだせる可能性もあるでしょう。
意識したい3つのポイント
さまざまなメリットを得られる生成AIですが、「うまく使いこなそうとすること」が大きな壁になることもあります。
たとえば、生成AIのような「いかにも最先端っぽい、すごそうなテクノロジー」が登場したとき、使う前から「よく分からない……」と萎縮してしまうことはないでしょうか。また、「1~2回は使ったことがあるけれど、それ以降は……」というパターンもあるかもしれません。
これらは、とくに生成AI初心者にありがちな「落とし穴」にハマった状態であると言えます。では、こうした穴に落ちない、もしくは穴から脱出するためにはどうすればよいのでしょうか。3つのポイントをまとめてみました。
①小さな成功体験を積み重ねる
「継続は力なり」という言葉もあるように、生成AIも、本当に少しずつでもよいので使い続けることがとにかく重要です。
たとえば、「●日に1回は使う」といった目標をできる範囲で定め、「今日はこの作業を生成AIに頼んでみよう」「ここはこうすればできるかも?」「この作業は生成AIには難しそうだな」といった小さな成功体験や気づき積み重ねていけば、生成AIがもたらしてくれる価値におのずと気づけるようになるはずです。
②アウトプットに期待しすぎない
先述のとおり、一般的な生成AIはその用途を拡大しつつアウトプットの質も着実に向上させています。しかし、「なんでもできる!」と最初から期待しすぎると、狙いどおりのアウトプットが得られなかったときに「あれ? こんなもの?」と肩すかしを食らうことも。
その結果、1~2回使ってサヨナラ……。これは非常にもったいないことです。①にも通じますが、まずは簡単なところから始め、「できそう」という感覚を少しずつ獲得することが大切になります。
③誰かと一緒にさわってみる
仲間のチカラを借りてモチベーションを高める方法は、新しいことに挑戦する際に効果的です。生成AI初心者同士であっても、ワイワイと会話をしながらさわるほうが1人よりも楽しいですし、いろいろなパターンを試すことができるでしょう。
とくに、初めて生成AIをさわる人には「初回だけ社内外の有識者に教わる」といった手法もオススメです。「生成AIを使う予定だから自習しておいて! と言われるとちっともやる気が出ないけれど、誰かと一緒ならできる!」という人は、意外と多いかもしれません。
「入口でココロが折れない」選びかた
ひとくちに生成AIといっても実にさまざまな種類があり、それぞれの特徴も異なります。「とりあえず使ってみる」前に、どのようなモノを選べばよいか、ざっくりとした方向性を知っておくとよいでしょう。
「使うタイミングの分かりやすさ」を重視
「鍋=料理道具」といったように、使うタイミングが明確な生成AIにふれることは、利用に慣れていくうえで極めて重要な要素だと言えます。
たとえばChatGPTなどは新しい機能がどんどん追加されており、リリース当初よりもはるかに便利になっていますが、裏を返すと「複雑さを増している」とも言えます。実際、数回で利用をリタイアした方は、おそらく「●●に使える(使おう)」というタイミングや目的を見いだせなかったのではないでしょうか。
つまり、汎用性の高い生成AIを最初から無理に使おうとするのではなく、ある用途に特化した生成AIを選ぶことが小さな成功体験を生み出し、大いなる第一歩につながるのです。まずは身近な業務での困りごとをいくつかリストアップして、それらを解決できそうな生成AIを探してみましょう。
「使いかたの分かりやすさ」を重視
この要素は「操作画面がシンプル」や、「できることが明確」などと言い換えることもできます。できることが多岐にわたってしまうと、「あれもやりたい、これもやりたい」という欲求が生まれ、それが次第に「~しなければならない」という義務感に変わり、やがて疲れて果てて挫折する……といったことにもなりかねません。
「単体の生成AIだけで悩みを解決できなくなったら、そのあとにはじめてChatGPTなどとの併用を検討する」くらいの温度感で考えておけば問題ないでしょう。
1クリックで簡単! 「はじめて」にもオススメの生成AI
「使うタイミングや使いかたが分かりやすい生成AI」という観点において高い需要を発揮しているのが、議事録・日報などを作成してくれるツールです。たとえば「1時間の会議の議事録を作るのに、その数倍の時間を要している」「この時間を他のことに回したい……」そんな経験はありませんか?
そんな皆さまには、「おまとめ忍者」のようなツールの活用をオススメします。こうしたツールは基本的に使うタイミングが会議や報告時などとハッキリしており、かつ喋るかテキスト入力(コピー&ペースト)をしてボタンを1クリックするだけと、使いかたも非常に分かりやすい傾向があるからです。
ここで、「おまとめ忍者」の活用によって業務効率化に成功した、ある方々の事例を簡潔にご紹介します。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
【対象使い手の背景】
■指定の場所を毎日巡回し、レポートを手作業で作成して状況報告する業務を担当
■レポート作成に多くの時間を消費
■デジタル活用経験が浅く、自分のPCのログイン方法やメールアドレスが分からない
★「おまとめ忍者」の概要と使えるシーンを簡潔に説明し、利用開始★
【初期】
■手作業が音声(喋り)での入力に置き換わったことで、一定の労力が軽減
■使いやすさが奏功し、この段階から継続的に利用
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
【後期】
■報告内容にタイトルや見出しをつけはじめた(話す内容を整理できるようになった)
■「こうすれば忍者がうまくまとめてくれるはず」と自主的な工夫にも挑戦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
この事例では業務効率化もさることながら、「使い手が話す内容を整理できるスキルを身につけられた」という点も、非常に大きなメリットになったと言えます。周知のとおり、生成AIは学習して賢くなってゆくものですが、それは人間も同じです。つまり、生成AIは単に便利なツールであるだけでなく、使いかたや工夫の仕方によっては、ヒトを成長させる可能性も秘めているのです。
まとめ
今回は、生成AI初心者が活用の際に意識したいポイントなどを解説しました。
まずは以下の3点を意識し、現在のお悩みに合った生成AIを探してみるところから始めてみましょう。
①小さな成功体験を積み重ねる
②アウトプットに期待しすぎない
③誰かと一緒にさわってみる
また、後半では生成AIの活用によってヒトも成長できる点についてもふれましたが、そうした好循環も、そもそも使ってみなければ決して生まれることはありません。「まずは一歩を踏み出してみる」ことが、やはり何よりも大切です。
もし「③誰かと一緒にさわってみる」の仲間が必要でしたら、ぜひ下のバナーからマクニカのチームにお声がけください! いまこそ使ってみよう、生成AI!
