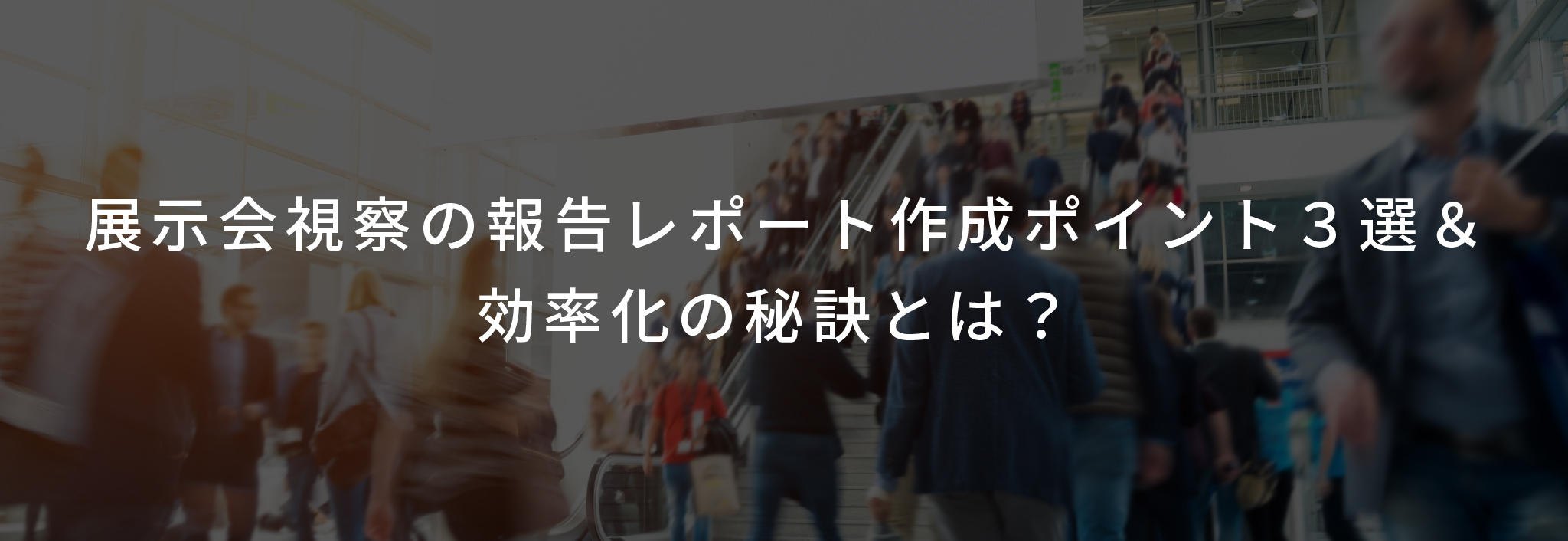
企業が自社製品やサービスなどを紹介し、プロモーションやブランディングなどを行う展示会。その開催数は年々増加傾向にあると言われており、視察にかかる時間的コストも必然的に大きくなっています。その一方で、「視察するからには良質な情報を持ち帰らなければ」……というジレンマに悩まされるかたも多いのではないでしょうか。
今回は、自ら展示会視察をするなかでさまざまな課題を抱えている「M部長」の悲劇的なストーリー(実話)を振り返りつつ、展示会視察の報告レポート作成におけるポイントを解説します。
M部長の現状と「あるある課題」
まずは、展示会視察にまつわる彼の現状と課題を整理してみました。とくに課題については、「あるある……」と思うかたもいらっしゃるかもしれません。
展示会視察の目的
M部長はどうやら、下記のような目的で展示会を視察しているようです。
■市場動向の調査
■パートナーの発掘
■お客様の発掘
なるほど、まさに「いかにも」といった内容です。読者の皆さまにも、こうした目的がメインの方がきっと多いのではないでしょうか。最新情報を現地のブースでいち早くキャッチしたり、思わぬ出会いがあったりするのは、展示会の大きなメリットです。
展示会場での立ち回り
そんなM部長は、展示会場で「入口から順に、気になったブースをひたすら訪れている」と言います。というのも、「最近は展示会の出展企業が多くて、情報を得たい企業を事前に絞り込むのが難しい。ドンピシャだ! と感じるのはせいぜい1~2社くらいだから」とのこと。
たしかに、出展企業が増えれば増えるほど訪れたいブースも多くなるのは自然な流れです。しかし、思いつくまま手当たり次第にブースを訪れる彼には、多くの悲劇が待ち受けていたのでした……。
4つの「あるある課題」
「では展示会視察での困りごとは?」と尋ねると、「そりゃもう、たっくさん!!」となぜか嬉しそうなM部長。さまざまな「あるある課題」を赤裸々に明かしてくれました。
①「サボっている・遊んでいる」と思われたくない
展示会の開催が年々増えているのは冒頭で述べたとおりですが、結果として「アイツ、いったい何回展示会に行ってるんだ?」などと思われることをM部長は何よりも恐れています。とくに海外出張は多額のコストを要するので、よりプレッシャーがかかるんだとか。
②得た情報を整理する時間がなく、情報共有が困難
展示会視察に訪れた以上は、チームに有益な情報などの「手土産」を持ち帰ることが必須ミッションとなります。しかし、多忙なM部長には自身が訪れた何十ものブースの情報をひとつひとつ丁寧に整理している時間は、とてもありません。
一方で、自身が重要だと思ったポイントだけに絞ってチームに共有した場合、そのボリュームはおよそ十分とは言えないはずです。結果、「さんざん時間をかけたのに、得られた情報はたったこれだけ?」と思われてしまえば、①にもつながってしまうでしょう。
③「重要なポイント」が人によって違う
たとえば100個の情報を展示会視察で得て、そのうち50番目を「とくに重要だ」と判断したM部長がピンポイントでチームに共有したとします。しかし、チームメンバーのなかにはもしかしたら97番目、あるいはもっと別の情報が重要な人がいるかもしれません。周りに伝えられる情報量に限りがあるせいで、本当に必要なことを必要な人に届けられないのは非常に厄介であり、もったいない問題です。
④忘れる
ヒトの記憶というのは、本当に頼りにならないものです。まして、1日にいくつも訪れたブースで見聞きしたことをすべて覚えていられる人が、どれだけいるでしょうか。もし「覚えている断片的な内容だけを、口頭ベースで周囲に共有」したなら、それは話し手自身でなく、相手の貴重な時間的コストまでもを奪うことになりかねません。
展示会視察の報告レポート作成ポイント3選
前述のような課題を抱えながら、「自分はそもそも視察報告レポートの提出がまともにできていなかった」と絶望するM部長。その背景をたどっていくと、視察において意識すべき3つのポイントが反面教師的に見えてきました。
定性的なインテリジェンスの獲得
「売上に直結する成果の獲得」を展示会視察だけで実現するのは困難ですが、「将来的なペイにつながるであろう情報の獲得」がROIにダイレクトに響くのは事実であり、非常に重要だと言えます。そして、そうした情報はえてして会場での雑談などからも生まれるものです。
たとえば、どの企業も自社のWebサイトにはキレイにまとめた情報を掲載しているのが常です。それらはある意味で、「定量的な情報」と表現できます。しかし、展示会場でやり取りをするのはあくまで人同士。質問の仕方によっては競合企業からWebに掲載されていないような、貴重な情報を訊き出せるかもしれません。
そうして独自に得た「定性的な情報(インテリジェンス)」を集めて自社のチームに共有できれば、少なくとも「サボっている・遊んでいる」と責められることはまずないでしょう。
主観によるバイアスの除外
会社で働く人々はみな個々のミッションをもっており、それぞれが必要とする情報も異なります。そのため、展示会には全員で視察に行くのがベストですが、残念ながら工数面の問題などから現実的でないことが多いでしょう。つまり、M部長のような人は「代表者」ということになります。
ここで重要なのは、「その代表者が情報を収集・整理する過程において、自身の主観で必要か不要かを判断すべきではない」ということです。得た情報をできるだけ多く、かつ生の状態で持ち帰り、関係者全員が見られるサイクルを回すことができれば、展示会視察というアクションには高い価値が生まれます。
ツールの活用
M部長は「情報を整理する時間がない」「忘れる」という、もはやヒトの成せる範囲ではどうしようもない致命的な課題を抱えていました。そこで着目したいのが、ツールの活用です。
実際のところ1日に何十ものブースを訪れたとして、そこで見聞きした内容を丁寧に資料化して共有……というのは非現実的です。手書きはもちろんのこと、PCやスマートフォンのメモ機能などへの打ち込みも、決してラクではないでしょう。しかし、「忘れない」ためには「即座に記録しなければならない」という厳しい現実もあります。
こうした問題をクリアにするために、昨今の優秀なテクノロジーの数々を活用しない手はありません。それに気づいたM部長は、あるツールとの劇的な出会いを果たします。
展示会視察の記録に役立つツール
窮地のM部長を救ったのは、「おまとめ忍者」という、生成AIを活用したツールでした。このツールは音声入力した内容をその名のとおり「おまとめ」し、さらに校正やポイントの抽出、次のアクション提案をおこなうなどの機能を有しています。
下記は、M部長がある展示会の1ブースで説明を聞き終えた直後に、「おまとめ忍者」を使って実際に残した記録です(一部抜粋)。
----------------------------------------------------------------------------------------------------
【ポイント】
・VOC分析ツールを確認し、プロジェクトの理解を深めた。
・AIで数万件の顧客声を分析し、逆ニーズを把握。
・競合のキャッチコピーが自社プロジェクトに類似。
・データ量に応じた料金設定がされている。
・インプットデータのフォーマット確認が必要。
・UIの確認ができ、訪問の価値を感じた。
・社内でのデータ利用方法についての考察。
【校正文】
このツールは、アンケートやユーザーの声を基にした素晴らしいUX分析が可能であり、彼らは仮想競合ベンダーであると理解しました。どの程度の施策提案が出てくるのか、無料で試してみたいと考えています。
日本では、わずか1時間で数万件のお客様の声がAIによって分析され、逆ニーズが明らかになるというキャッチコピーがあり、我々の開発しているプロジェクトのアプローチと非常に似ているため、ベンチマークを行いたいと思います。データの料金設定はデータ量に基づいているとのことで、例えばインプットするデータ数が数千件から数十万件に増えても、ユーザーの価格は変更されないとのことでした。
また、事例に顔が必要なことが強力であると感じました。ただし、インプットするデータのフォーマットについては不明な点があったため、確認が必要です。アンケートなどのデータフォーマットが統一されているため、プロジェクト側にデータがあるとのことでしたが、カスタマイズは行っていないようです。
このUIを見られただけでも、今日の訪問の価値がありました。素晴らしいWebでは見ることができなかった情報です。最後に、社内での利用に関して、プロとしての視点から、どのようにお客様の情報を活用しているのかを確認したいと思います。

M部長はブースで10分間の説明をうけ、そのあとわずか1分間でこの情報を作成したそうです。しかも、M部長がしたのはスマートフォンに向かって喋るだけ。文字の打ち込みなども一切行わず、この早さで情報をまとめられるなら、1日に何十というブースを回って大量の記録を残すことも現実的と言えるでしょう。また、チームに共有する際はテキスト化された内容をそのまま渡すだけでOKです。

話し相手にピンマイクをつけてもらえば会話内容をそのまま「おまとめ」してくれるので、自分で思い出しながら話さなくてもよい場合もあります(話者も識別可能)。
こうして①~④の「あるある課題」を見事に撲滅したM部長は足取りも軽く、次の展示会へと出かけてチームに貢献するのでした。
まとめ
今回は「展示会視察の報告レポート作成のポイント」を、実話を交えながらご紹介しました。
皆さんはいま、展示会視察の結果をどのように記録し、報告しているでしょうか。たとえば定例会の5分、10分という短い時間で展示会のことを簡潔に話さなければならないとき、大変な思いをしていないでしょうか。そのあとも必要な記録を残せているでしょうか。
もしうまくいっていないことがある場合は、今回ご紹介した以下の3点を意識し、とくに③の「ツールの活用」を視野に入れてみると活路を見いだせるかもしれません。
①定性的なインテリジェンスの獲得
②主観によるバイアスの除外
③ツールの活用
レポート作成を効率化し、展示会ライフをよいものにしましょう!
