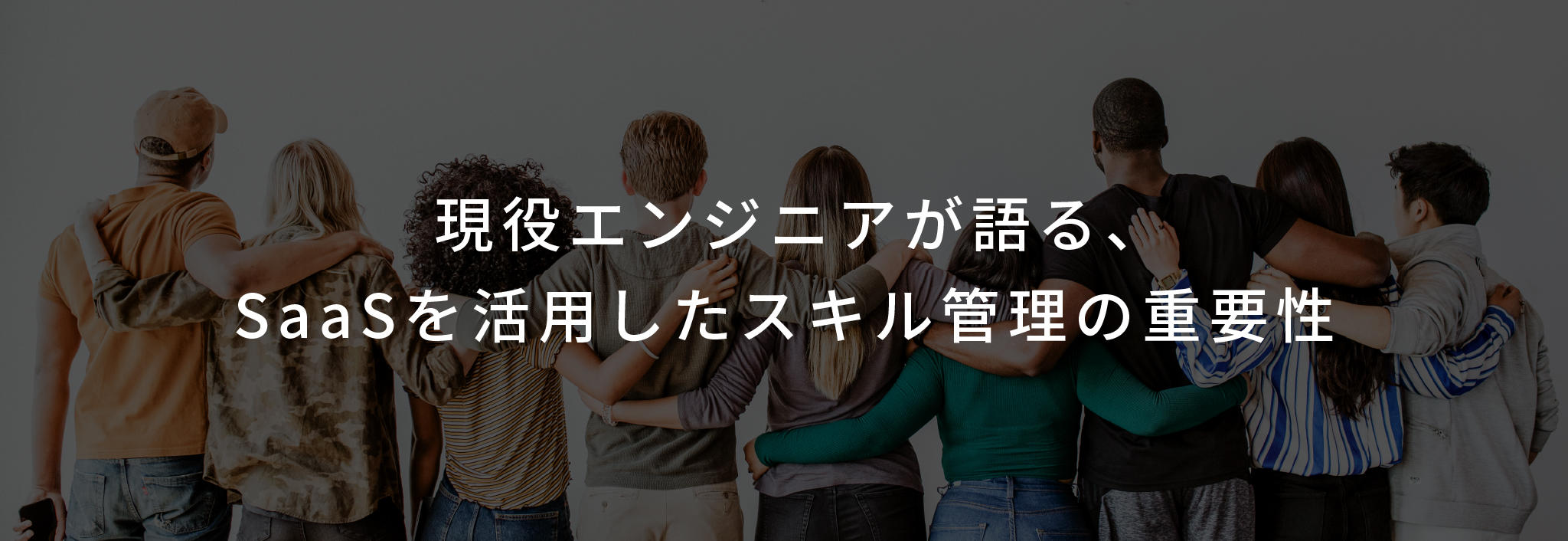
個々の社員がもつスキルの適切な管理は、チームがよい結果を残すために不可欠な条件のひとつと言えます。その実現をサポートするのが、マクニカが開発を手がけるツール「Zipteam」です。今回は、豊富なエンジニア経験を活かしてその開発に携わる吉川 大地に、Zipteamにかける想いを訊きました。
スキルを適切に活かせる環境づくりのために
――Zipteam開発の背景を教えてください。
吉川:「SaaSを介して人材のアサインが適切に行われることで、チームが生み出す結果のベースラインを底上げしたい」と思っています。
私はいくつかの企業でエンジニアを経験してきたのですが、そのうちのひとつで「エンジニアを適当にローテーションしすぎでは?」と感じていました。エンジニアといっても、実際にはソフトウェアやハードウェアなどさまざまな種類があります。分かりやすく料理人にたとえるなら、タイ料理の屋台やフランスの高級レストランのように、各自の得意分野がまったく異なるわけです。
とはいえ、メンバーを振り分けるマネージャーなどに対して1人ひとりの得意分野やスキルを細かく紹介することは難しいので、「この程度は知っておいてください」というのは酷な話です。エンジニアだって営業の業務や必要なスキルをあまり知らないように、他の職種の解像度は低いのが常ですから。
しかし、なぜか一部のエンジニアや営業は、万能で適応性が高いと勘違いされます。結果、「あなたは料理人だから料理ができるのでしょう?」と一緒くたにされ、屋台料理を得意とする人が高級料理店を任されるようなミスマッチングが、とくに大企業では起きがちです。さらに不適切なローテーションをされた人が「できるふり」をしてしまうと、全員が不幸になります。

一方、中小企業では1人が多くのものを抱えていることが少なくありません。私が以前務めていた会社にDevOpsのエンジニアがいたのですが、DevOpsに詳しい人間が他にいなかったので、彼に任せきりになっていました。その後、彼が退職することになったとき、私たちは「何ができなくなるんだっけ?」と焦りました。結局、みんなで協力してどうにか彼の業務をリストアップしたのですが、とても優秀な彼と同様の人材をふたたび雇うことはかなわず、残ったメンバーで手動による業務分担をしました。
このように、エースが退職やローテーションによってチームから抜けることは珍しくありません。それを見越して個々のスキルを把握しておき、適切なチーム再編に備えられているマネージャーは、おそらく世の中にそういないのではないでしょうか。もし空いた穴を適当に埋められてしまうようなことがあれば、やはり全員が不幸になります。私はエンジニアの視点から、そういった事態は回避されるべきだと考えるようになりました。
チーム編成はメンバーと実際に話したほうが精度が高くなるとは思いますが、何千人もの社員が相手となると、それは現実的ではありません。だからこそ、スケーラブルにするためにはZipteamのような情報管理ができるSaaSの活用が必要です。

――そういった課題を解決するサービスは、これまでにはなかったのですか?
吉川:そうですね。HRで導入されるソフトはよくスキル管理と紐づいていますが、実際の現場で使われているスキルの詳細まではスコープ外だと思います。そのスキルを管理するのは、各部門のマネージャーですから。HRのソフトウェアで段階を飛ばしてしまうと正しいスキルデータは集まりませんし、現場がやりたいこととの齟齬も生じてしまいます。
人事という言葉にも原因があるように思いますが、「人に関わることはすべて人事が行う」という勘違いを、HRの担当者と現場の両方がしている感じでしょうか。これはとても日本的で、たとえばアメリカのGoogleではもっと人事権が分散しています。現状の日本にはこうした状況を打開できるソフトウェアはなく、トラディショナルな大企業に即した、人事目線のサービスが中心になっていると感じています。
以前、ある会社に作られた自分のスキルリストを見る機会がありました。非常に長いリストだったのですが、私が過去に研究所で身につけ、当時の武器としていたROS(ロボットオペレーティングシステム)の記載はそこにありませんでした。当時いた会社ではそれ以外のスキルに注目すべきということだったのでしょうが、研究所ではROSが高く評価されていたわけです。こうしたギャップの解決は、現存のサービスには難しいかもしれません。
――Zipteamの開発にあたって、どんな点を意識していますか?
吉川:これはある方の受け売りなのですが、「プロダクトがストーリーを語っているかどうか」は意識しています。
たとえばある人に工具箱をポンと渡すだけでは、その相手が「これを使って何をしようかな?」と迷ってしまいます。そうではなく、工具箱を開けたときにすべきことが明確になっており、かつユーザーに適度な自由度があるのが私たちの理想です。一例として、ある機能にはユーザーがやろうと思えば無限にデータを登録できるようになっていたのですが、「上限があったほうが安心だし、やりたいことは十分にできるのでは?」ということで、30個までに制限しました。
私たちはUI/UXのエキスパートではないので常に学びながらですが、メニューの順番を工夫したり、優先度が高くない部分が目立たないようにしたりといった点にも細心の注意を払っています。
一方で、ユーザーフィードバックのすべてをストレートに受け取りすぎないことも心がけています。これは有名な話ですが、かつて、ある会社がさまざまな色のCDプレイヤーを開発し、公募したテスターにどの色がよいと思うかのアンケートをとりました。テスターたちはアンケートに「黄色が鮮やか」などと答えたものの、「どうぞ好きなものを1つお持ち帰りください」と伝えると、こぞって黒を選んだのです。

ユーザーがフィードバックをするときは、たいてい「よい意見を言おうとするモード」になっている傾向があります。私たちはその真意を真剣に考えつつも、「○○が使えない」などと言われてもショックを受けすぎないように振る舞っています。
ただ、チームアップ(チーム編成)はユーザーに必要とされる機能の2歩先をゆくもので、正直なところ作るタイミングが早すぎたかもしれないと思っています。IoTやDXなどもそうでしたが、先進的なものは世の中にすぐには受け入れてもらいにくいものです。
Zipteamでいえば、私たちはスキルの可視化において皆さんが引っかかるであろう部分を理解しているので、それを踏まえたうえで必要な機能を提供します。そして、そのスキル可視化の先にあるのはチーム作りです。ところが、世の中は「スキルを可視化して見たい」という1歩先の部分にもまだ到達していません。そんな状態で、チーム作りという2歩先のところで使うべき機能を私たちは先に作ってしまったわけです。
そんな状況でもこの機能をリリースしたのは、すでにその2歩先にたどり着いているお客様の協力があったからです。
――世の中がその1歩、2歩先にたどり着くためにはどんなことが必要だと思いますか?
吉川:実際のところ、すでにたどり着きつつあるアーリーアダプター的な会社もあると思います。スキル可視化の部分ではコンペティターも現れ始めているので、そこも盛り上がってほしいなと。自分たちとしてはオーソリティの協力も得ながら、スキル可視化の大切さを伝えるメッセージを発信していきたいです。
個人の尊重も重要なミッション
――Zipteamはどんな方に活用してほしいですか?
吉川:大きく分けると、CXO・各部門のマネージャー・個人の三段階で考えています。いわゆるHRのソフトウェアを使っている会社の場合、「自分はエンジニアと入力したのにサポートに回される」といったことも少なくありません。それなりに入力時間がかかる割に、ユーザーに対するメリットの還元率が低いわけです。しかし、個人が輝ける場所はきっと誰もに存在します。だからこそ、私は当初からユーザーにベネフィットがあるようにと考えていました。
個人の場合は自分を正しく認識してもらうことで社内のプレゼンスが高まりますし、自分のスキルを活かせないチームに配属されそうなら、可視化したスキルグラフをもって反論すればよいのです。そうしたデータは適切な人材のアサインにつながるのでマネージャーにも重宝されると思いますし、「現場はうまくやっていたはずでは……」というCXO目線の見えないギャップも払拭され、コンサルタントを雇うコストも不要になったうえで会社全体の生産性はアップします。

――スキルの可視化がされていないことによる問題点は、改めて考えてみるとかなり多い気がします。「この人の経歴とスキル、実は隣の部署ですごく活かせるのに」といったケースもよくありそうです。
吉川:そうですね。結果、だんだん知っている人としか仕事をしなくなることも少なくありません。それも悪くはないのですが、他で輝ける可能性を活かせないのは、非常にもったいないと思います。
とはいえ、Zipteamを1,000人のユーザー向けに導入したとしても全員がいきなり使ってくれることはまずないでしょう。そのため、基本的にはマネージャー層のかたにリードしてもらうことを前提に考えていますし、すでに導入いただいているお客様はそのような使い方をされています。
――だからこそ今後は企業に数人のみの人事だけではなく、マネージャーのかたがたも人事権をもつ必要があるということですね。そのほか、開発者目線でユーザーに伝えたいことはありますか?
吉川:最適なチーム編成にはスキルだけでなくカルチャーフィッティングも重要ですが、その成功を目的としたパーソナリティの管理はZipteamでは行いません。気質や性格診断などで個人を管理してしまうと、それがその人にすべてに見えてしまい、ミスリードになるからです。それに、もし外向的か内向的かなどを可視化してしまえば、おそらく多くのマネージャーはおそらく外向的な人に優先的に声をかけるはずです。
「スキルもパーソナリティもマッチしているから、あなたはこのチームを抜けられません」という判断はやはりその人を不幸にしますし、気が合うことと仕事の成功もまったく別の話です。個々とのコミュニケーションを重んじるという意味での余白は残しつつ、チーム編成が単純化されすぎないようにしたいですね。
一方で「実は○○が好きでずっと取り組んでいます!」といった、ポジティブにしか働かない情熱に関してはシェアする価値があると思っているので、そういった機能はいずれ実装するかもしれません。
Zipteam開発に関して、同じチームには5年以上の先を見据えているメンバーもいますが、私は意識しているのは現在のマイルストーンとその1歩先あたりです。プロジェクトの中心にいる人はビジョナリーなことを期待されがちですが、私のような者もいるということは、読者の皆さんにも伝えておきたいところです。
おわりに
今回は数々の現場を渡り歩いてきた、吉川ならではの経験談からスキル可視化の大切さを知ることができました。自社に必要な人材の方向性を明確にし、よりビジネスを拡大したい皆さまとコラボレーションできる日を、私たちはとても楽しみにしています。チームのパフォーマンスを高め、暗黙知から生まれるイノベーションを実現する「Zipteam」についてより詳しくご覧になりたい方は、下記の公式ウェブサイトもぜひご覧ください。

