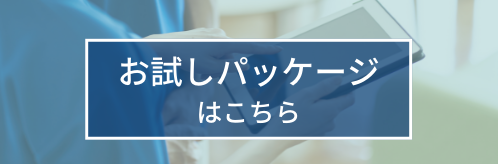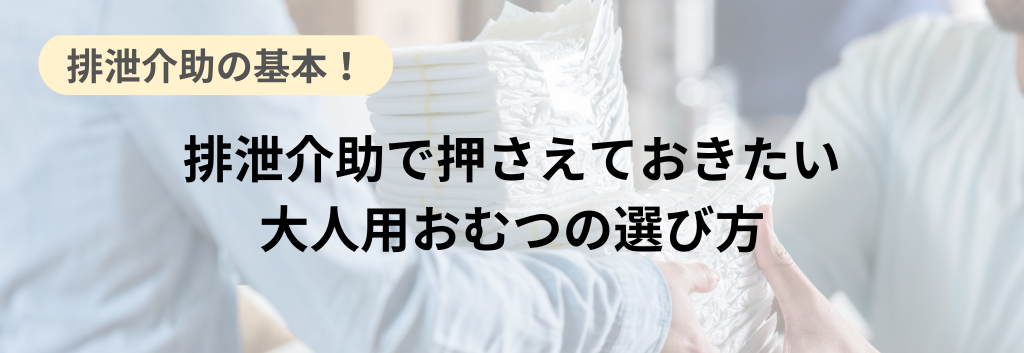
大人用(介護用)おむつのタイプ別特徴と選び方のポイント
大人用おむつを大きい分類に分けると、「リハビリパンツ」と「テープ止めおむつ」があります。
リハビリパンツとは、いわゆるパンツタイプのおむつのことです。
下着のような感覚で使用するため、自力でトイレに行かれる方、もしくは介護付きでトイレに行くことができる方に向いている排泄用品です。
近年ではうす型化されているため、着用後のシルエットがより自然で、使い心地も良いものになってきています。
テープ止めおむつは、名前の通りテープで止めるタイプのおむつです。
下着のように履くリハビリパンツとは異なり、ベッドに横になったままでも交換しやすいため、寝たきりの方のための排泄用品として使用されることが多いです。
また、吸水性が高く、尿取りパッドと併用することで、よりおむつ交換の負担を減らすことができます。

リハビリパンツ

テープ止めおむつ
リハビリパンツとテープ止めおむつ|それぞれに向いている人は?
リハビリパンツに向いている方
・自分で立ち上がれる、歩ける
・トイレに行けるが、時々間に合わない
・尿意・便意がある
・排尿後に漏れが不安(腹圧性尿失禁など)
・下着+パッドだけでは不安 など
テープ止めおむつに向いている方
・寝たきり、または座位保持が困難
・トイレに行けない
・夜間の失禁がある
・介助者による交換が必要
・長時間の吸収が求められる など
排泄介助の負担軽減も重要ですが、選び方を誤ると本人の身体機能や排泄機能の低下につながる恐れがあります。
本人のADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)を最優先に考え、以下のポイントを押さえて選びましょう。
適切なタイプの選び方と注意点
排泄用品は種類が豊富で、どれを選べばよいか迷う方も多いのではないでしょうか。
製品を選ぶ際にはいくつかのポイントを押さえておくことが大切です。
①吸収量
同じメーカーでも、「長時間用」と「うす型タイプ」があり、うす型のほうが吸収量の少ないものがほとんどです。
種類によって差はあるものの、リハビリパンツは3~5回、テープ止めおむつは2~4回吸収できるものが多いです。
本人の尿量やトイレの回数など考慮し選定しましょう。
②サイズ
S〜LLなど複数サイズがあり、メーカーによってサイズ感が異なります。
ウエストやヒップのサイズ表示を必ず確認し、本人に合ったサイズを選んでください。
サイズが合わないと漏れや不快感の原因になります。
③通気性・質
長時間の装着で皮膚トラブルが起こることもあります。
通気性の良い素材や弱酸性の肌に優しい製品を選び、赤みなどが見られる場合は保湿剤でケアしましょう。
④ 性別や使用シーンも考慮
一部メーカーでは、男性・女性それぞれの排尿位置や体の形状に配慮した専用設計のおむつも販売されています。
また、「夜間用」 「外出用」などシーン別の製品を使い分けることで、より快適に過ごすことができます。
おむつで漏れてしまう原因と対処法
おむつを使用しているのに、衣類まで濡れてしまう…という悩みを抱える方は少なくありません。
このような「漏れ」の原因は、おむつの選び方や使い方に起因することがほとんどです。
以下のようなケースを見直すことで、漏れを防ぐことができます。
・サイズが合っていない
おむつが大きすぎると、足の付け根に隙間ができて尿が漏れてしまうことがあります。
足回りやウエストサイズに合ったおむつを選ぶことが大切です。
また、テープ止めおむつで隙間ができてしまう場合は、その上からリハビリパンツを履いて固定する方法も効果的です。
・正しいつけ方ができていない
おむつは、使う前にきちんと準備することが重要です。
たとえば、テープ止めタイプでは「足ぐりのギャザーをしっかり立てる」
リハビリパンツでは「両手を入れて数回横に広げる」など、事前のひと手間がフィット感に大きく影響します。
・吸収量が足りない
サイズや装着方法に問題がないのに漏れてしまう場合は、吸収量の不足が考えられます。
厚手のおむつに変更したり、尿とりパッドを併用するのが効果的です。
特にリハビリパンツを使用する場合は、マジックテープ式のパッドの方がずれにくく、おすすめです。
また、パッドを併用することで、おむつ自体の交換頻度を減らせるため、費用面や介護の負担軽減にもつながります。

また、排尿に気づけない方もいるため、介護者がこまめに状態を確認することが、尿漏れの予防につながります。
その際は、本人の気持ちやプライバシーにも配慮しながら、負担を感じさせないサポートを心がけましょう。
見守りシステムで睡眠状態を把握し、覚醒時に介助することで、安眠を妨げず、最適なタイミングでのおむつ交換による快適性向上も期待できます。
おむつ費用の負担が気になる方へ
・おむつ支給制度
要介護認定を受けた高齢者や障がいのある方に対して、紙おむつや尿取りパッドを月ごとに定量支給する制度です。
支給方法は自治体によって異なり、現物支給、購入費の助成、または補助券形式などがあります。
多くの場合、要介護度・所得制限・在宅介護であることなどが条件となります。
・医療費控除
要介護者で医師の指示によりおむつが必要とされた場合、おむつ代を医療費として確定申告できるケースもあります。
医師の「おむつ使用証明書」などが必要ですが、年間の医療費が一定額を超える方にとっては、費用軽減に役立ちます。
これらの制度は自治体ごとに条件や手続きが異なるため、市区町村の介護福祉課、または地域包括支援センターに問い合わせるとスムーズです。
申請には、要介護認定通知書・所得証明・医師の証明書などが必要になる場合があります。
支援を受けられるかどうかはケースバイケースのため、まずは相談してみることが大切です。
関連する情報
お問い合わせ
当サービスに関してご質問などありましたら、以下よりお問い合わせください。