現在でも「Attentive Connect™」で入居者様の呼吸やバイタルなどは把握できていますが、今後は入居者様の生活リズムもデータとして蓄積されていくと、さらに使い勝手がよくなるのではと考えています。
たとえば「この方は何時くらいまで寝て、何時くらいに起きる」ということが分かり、それに応じた事前通知が届けば音で通知しなくてもよくなりますし、職員も心構えができるはずです。
また、以前ご紹介いただいたカメラもセットで導入できればより安全度が高まるので、そちらもぜひ検討したいと思います。


■企業情報:
南方グループホーム翔裕園
■事業内容:
平成17年4月15日に開設され、認知症対応型共同生活介護のサービスを提供。
また、平成18年4月1日からは介護予防認知症対応型共同生活介護の指定も。
2ユニット18名が利用可能なグループホームとして運営中。
■インタビュー対象者:
管理者 伊藤 圭亮様
グループホームは認知症を有する高齢者の方々が共同生活を営む場です。個室でプライベートの時間を確保しつつ、リビングやサロンでは皆様で過ごされる交流の時間をもてるなど、暮らしのなかでもメリハリのある環境となっております。
一般的な高齢者施設ですと事務所などからでもフロアを一望でき、入居者様の動きを常に確認しやすい傾向がありますが、入居者様の生活の質を高めつつ、ストレスをできるだけ軽くする事も重要だと私たちは考えています。
その一方で、当施設には多くの場所に死角があることが課題でした。実際、毎月2~3件ほどのヒヤリハットが挙がっており、「いずれ入居者様が転倒や骨折といった事故に遭われてしまうかもしれない」という懸念があったのです。
たとえば、入居者様が1人で歩いてトイレに向かわれる場合、足どりが不安定で危険な場合こともあるため、普段は職員が駆けつけて誘導していました。
しかし、とくに夜間では職員が気付く前に移動されていたなど、支援が必要なタイミングが読めない部分もありました。また日中であっても、食事の準備などをしている最中は同様のリスクがあります。
こうした状況を好転させるため、緊急の対応策を講じる必要があると私達は考えました。とはいえ職員の人数は限られており、巡視の回数を増やすにも限度があります。マンパワーの限界を乗り越えるには、やはり機械の力が必要だと感じました。そこで紹介会社に協力を求めたところ、マクニカ様をご紹介いただきました。
マクニカ様からは、入居者様の離床時や異常時の検知ができる「非接触ベッドセンサー」と、そのデータを閲覧できる「Attentive Connect™」をご案内いただきました。
選定の決め手になったのは、設置が非常に簡単だった点です。私たちの場合はとにかく速やかに対応策を打ち立てなければならない状況だったので、すぐ簡単に使えるという点は本当に助かりました。
私は他施設に勤めていた際、そこで他社の見守りセンサーなどを使用していたのですが、
センサーをベッドの脚に取り付けるタイプだったので持ち上げる必要があったりと力仕事になり、特に女性職員の場合は労力と時間を要していました。
しかし、この「非接触ベッドセンサー」は薄いセンサーマットをマットレスの下に設置し、コンセントを挿してPCの動作確認をするだけでよいので、かかる時間、労力が圧倒的に少なくて済みます。ある入居者様のベッドに設置していたとしても、そこから別の入居者様のところに移動させやすいこともメリットですね。
ほかには、アラートを出す時間帯を毎回個別に設定できる点が便利だと感じました。たとえば、ある入居者様の場合は、夜間の一定時間のみアラートが鳴るようにしています。対応できる職員の数が少ない夜間だけに的を絞れるのは、大変ありがたいです。
導入に際して、当施設では職員における対応の優先順位を定めることにしました。というのも、グループホームでは業者様、入居者様のご家族来園などさまざまな方への対応に加え、外線、内線などの電話対応も行っています。仮にこの全ての状況が同時に発生したなかで、さらに「Attentive Connect™」のアラートが鳴った場合、最優先でアラートの入居者様の下へ駆けつけるというルールです。
来客や電話の場合は「少々お待ちください」や「折り返します」で済みますが、アラートを後回しにした結果、起こらなくてもよかった何かが起こってしまった……ということだけは、絶対に避けなければなりません。
ただ、アラートが鳴ってもその音が聴こえなければ意味がないので、「Attentive Connect™」を起動中のパソコンの音量は常に最大にしておき、音量を変更してはならないというルールも設けました。
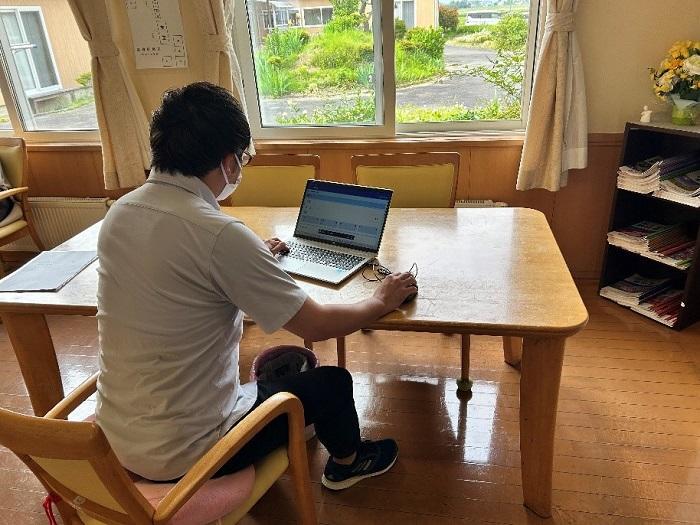
以前は生活音や料理の音などでアラートが聴こえにくかったこともあったので、ポータブルスピーカーを導入するなど、環境を整えたりもしました。現在では、料理の最中などでもパソコンを見えるところに運んでおくようにもしています。
また「非接触ベッドセンサー」の導入初期は、ホーム内で一番奥の居室の入居者様のベッドで使っていました。しかし、やがて「アラートが鳴ってから駆けつけるまでに時間がかかる」という声が職員から挙がってきました。そこで、その入居者様のご家族様にも相談のうえ、事務所やフロアなどからもっとも近い場所にその方の居室を転室させていただきました。
このように入居者様の安全対策を導入したことで、職員のなかでも新しい気づきがあり、リスクに対する意識も相当に高まったようにも感じます。
当施設では「非接触ベッドセンサー」と「Attentive Connect™」の導入から1年半ほどが経ちますが、とくに1日の巡視の回数が20~30回減ったことが大きな変化です。月に2~3回あったヒヤリハットも、導入後は2ヶ月に1回ほどになりました。
従来は1時間に1回の巡視に加え、物音がしたときなど何かあればすぐに確認していたのですが、いくら安全のためとはいえ、入居様もたびたび職員が見に来て落ち着かなかった
はずです。不必要な巡視が減ったことで、しっかりお休みいただきながら、かつ安全を確保できる環境づくりができたと思います。
また職員も同様で、「いつ対応が必要か分からない」とビクビクしていた部分があります。巡視の回数が多いと移動が増え、疲労も蓄積されます。しかし、現在はパソコンの画面である程度は状況を確認できるので、「肉体的、精神的な負担が大幅に軽減された。本当に助かった」という声も実際にありました。とくに夜勤は職員の数が少ないので、そのぶん効果が大きいですね。
安心感という意味では、入居者様のご家族も同様です。機材の詳細はもちろん、リスク軽減について説明をさせていただくことで、よりご安心いただけたのではないでしょうか。実際、ご家族の方がお越しのときにアラートが鳴り、その場で対応しているところをご覧いただいたこともあります。
安全面は勿論ですが、職員の生産性の向上の面からも、導入前の状態に戻ることは考えられません。これからも私たちの手が届かない部分に関しては、上手に機械の手を借りながら施設環境の整備に努めていきたいと思います。
現在でも「Attentive Connect™」で入居者様の呼吸やバイタルなどは把握できていますが、今後は入居者様の生活リズムもデータとして蓄積されていくと、さらに使い勝手がよくなるのではと考えています。
たとえば「この方は何時くらいまで寝て、何時くらいに起きる」ということが分かり、それに応じた事前通知が届けば音で通知しなくてもよくなりますし、職員も心構えができるはずです。
また、以前ご紹介いただいたカメラもセットで導入できればより安全度が高まるので、そちらもぜひ検討したいと思います。

Attentive Connect™ 情報Topページへ戻りたい方は、以下をクリックください。