
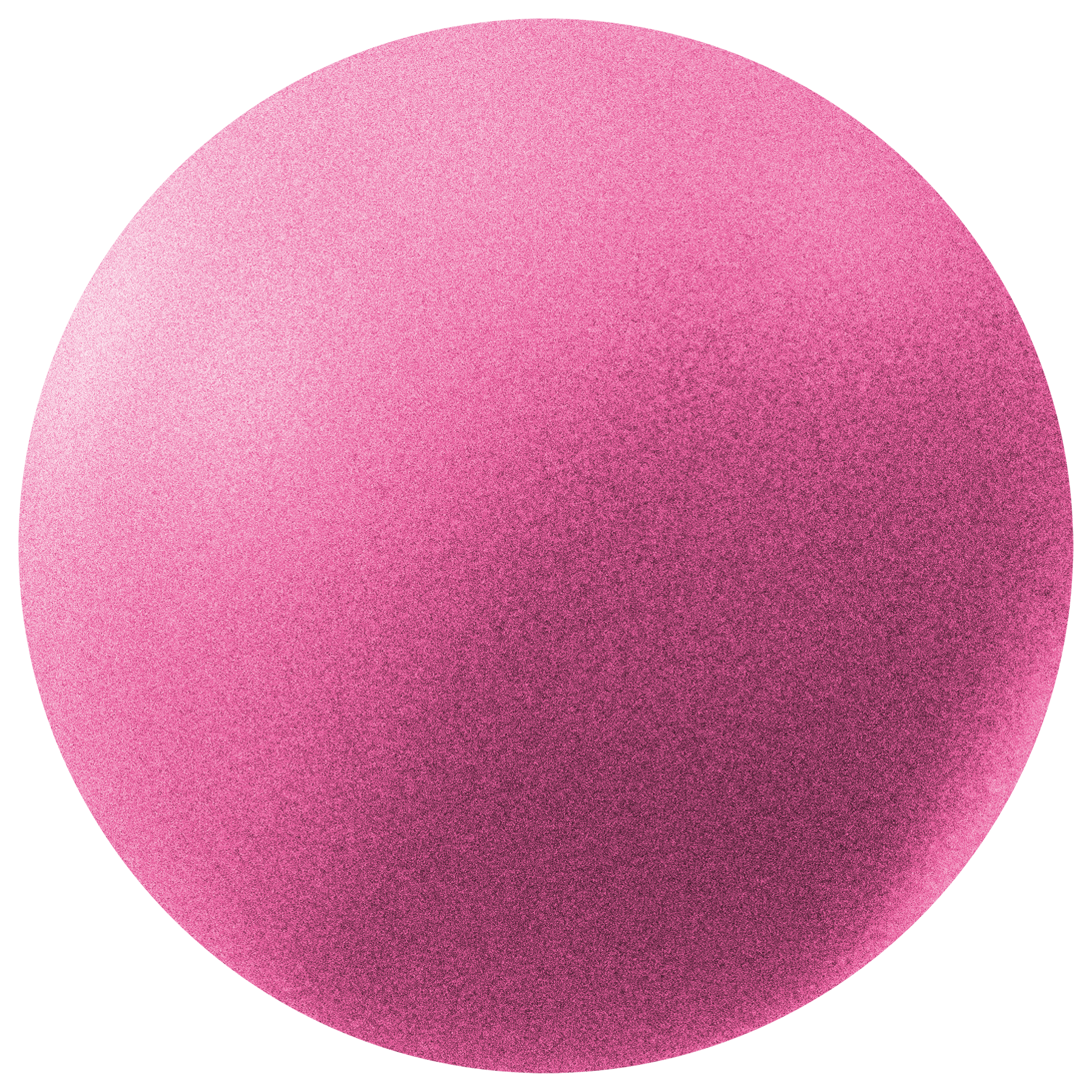
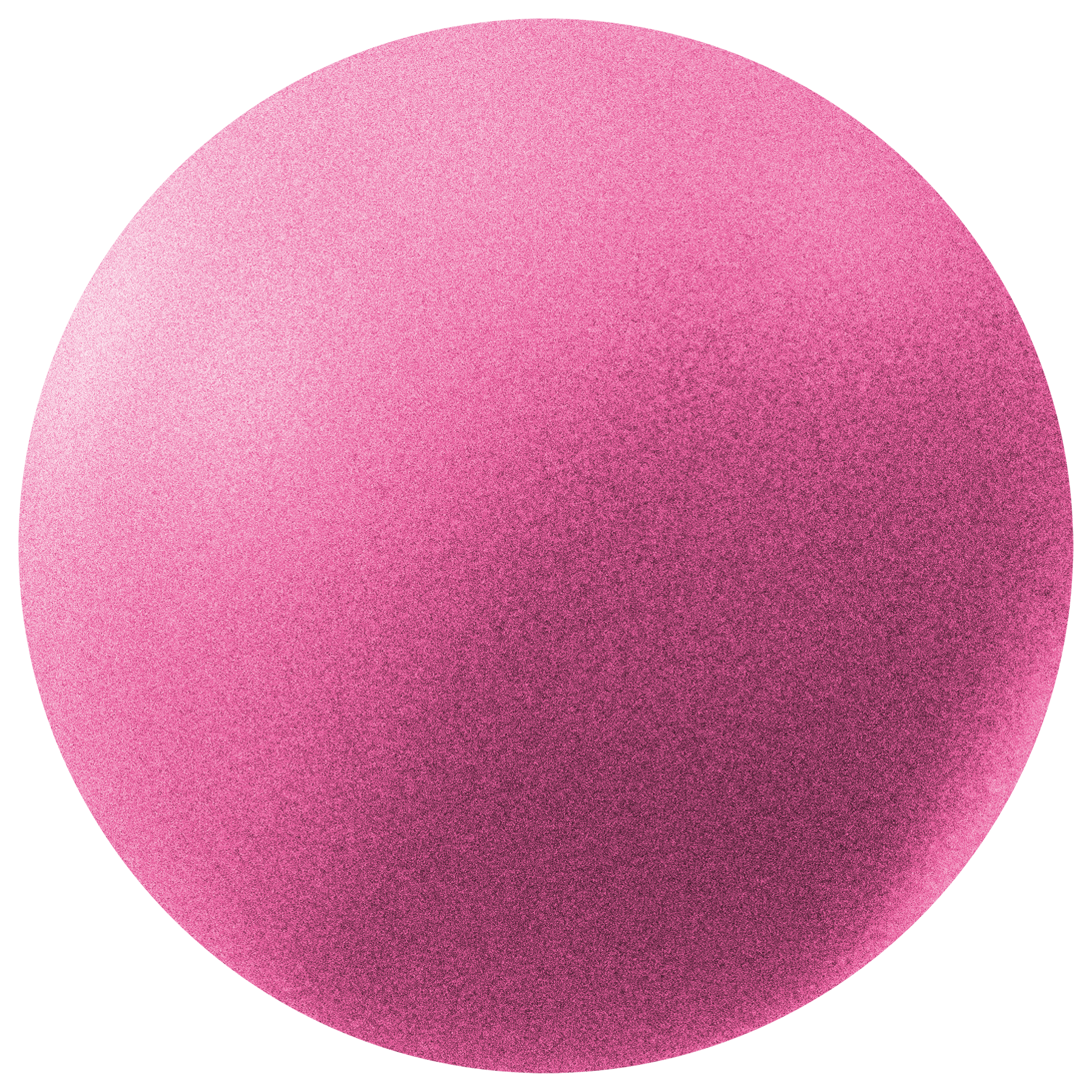
CPSソリューション
事業のタネは世界の食糧問題を解決する
『技と知の掛け合わせ』
OUTLINE
パンデミックや経済ショック、紛争、気候変動が重なり、世界中でかつてないほどの食糧危機が発生している。
マクニカは高い技術と品質を誇る日本の農業に着目し、効率性の向上にイノベーションの余地を見出す。植物の生産方法に革新を起こそうとしていた企業「NEXTAGE」と共同でプロジェクトを進め、自分たちが提供できる価値を徹底的に模索した。
その結果、NEXTAGEの栽培ノウハウと、それを具現化するマクニカのテクノロジーを掛け合わせ、今までにないブレイクスルーを起こす。栽培管理の効率化により高品質・大量生産を実現する「生育データ可視化システム」を、半月というスピードで開発したのだ。
PROJECT MEMBER
-

カンヌサミスンダララジャ
カピレッシュ新卒入社
-

長谷川 さくら
新卒入社
-

小林 俊介
中途入社
-

本村 健登
新卒入社
POINT
-
タネが生まれるまで
- かつてないほどの世界的な食糧危機
- 食品の効率的な生産を可能にする植物工場を普及させる必要性
-
タネを育てる
- 日本の農業におけるイノベーションの余地に着目
- アグリテックビジネスに注力する「NEXTAGE」との共同プロジェクト
-
タネの芽吹き
- 生育データ可視化システムの開発と実装
- 安定した高品質栽培の実現見込み
プロジェクト発足のきっかけ
互いの想いに共感する、運命の出会い
マクニカは考えた。「世界の食糧問題を解決するためには、食品の効率的な生産を可能にする植物工場の普及が必要だ」。そして、「人々の健康的な生活を実現するためには、植物工場で生産される食品が安全かつおいしいものである必要がある」と。
そこでマクニカは日本の農業の実態に目を向けた。日本は農業分野において高い技術を持った数少ない国。しかし、高品質を重要視するあまり、効率的な生産方法が確立されていないという特徴が見えてきた。マクニカは、ここにイノベーションの余地があると考えた。
「日本の農家の知見やノウハウによる高品質かつおいしい食品を、マクニカのテクノロジーを活用し植物工場で効率的かつ持続的に大量生産できるようになれば、世界を変えられるかもしれない」。そのような考えを持っていたマクニカは、ある日NEXTAGEという企業と出会うことになる。
NEXTAGEはアグリテックビジネスに注力しており、農業に従事する人々の高齢化や環境問題によって農作物の生産が難しくなっている状況に対し、「日本の食文化を守りたい」という想いで生産方法に革新を起こそうとしていた。
出会うべくして出会ったこの二社は互いの想いに共感し、共同でプロジェクトを進めることになる。水温や気温、日照時間など、栽培条件の管理が難しい農作物の大量生産を実現するソリューションやビジネスモデルを構築すれば、さまざまな食品の大量生産が可能になるかもしれない。こうしてマクニカの挑戦が始まった。

プロジェクトの挑戦ポイント
自らが提供できる価値を、徹底的に模索する
大きな目標を掲げて始動したプロジェクトだが、開始早々行き詰まることとなる。
誰もがどこでも農作物を簡単に栽培でき、世界中に届けられるようになるためには、システムを新しく構築する必要がある。しかし、マクニカはプロジェクト当初「そのシステムをどのようなものにすべきか」という答えをNEXTAGEに求めてしまい、システムの構築に関する議論が前に進まなかったのである。
「NEXTAGE様は植物工場の専門家ではありますが、テクノロジーの専門家ではありませんでした。テクノロジーの実装のためには、私たちが業界特有の知識と最先端テクノロジーを繋ぐ必要があることにプロジェクトの途中まで気づけていなかったのです」と小林は語る。
自分たちのミッションを再認識したマクニカは、「自分たちがこのプロジェクトにおいて何を価値として提供できるのか」「どのようなシステムを作れば目指すべき目標を達成できるのか」を明確にするべく、あらゆる情報を収集した。マクニカがテクノロジーのプロフェッショナルであっても、そのテクノロジーが目的を達成するものでなければ意味がないからだ。
マクニカは、生産工場を視察したり、さまざまな品種を試食したり、更には大学や専門家のヒアリングを通して、農作物の生産に関する幅広い情報を吸収し、自分たちがこのプロジェクトで提供できる価値を徹底的に模索した。


プロジェクトの成果
最先端システムを、驚くべきスピードで実現
マクニカはさまざまな活動を通して、農作物の大量生産を実現するためには、大きさや色見などのデータを数値化し、栽培管理を効率化した上で、栽培難易度を下げることが大切であると考えた。しかし、ここでもまた壁にぶつかってしまう。
各種データを取得するための適切なセンサーがまだ世の中に存在していなかったのだ。当初この壁を乗り越えることは困難であると思われたが、マクニカのデータサイエンティストたちが徹底的に議論を重ね、知恵を出し合った結果、解決の糸口を見つけた。
「形状が異なる物体の大きさやカメラからの距離にばらつきがある複数の物体を測定するAIの開発は何度か経験していました。そこで、既に我々が開発したことのあるAIを活用すれば、この問題を解決できるのではと考えたのです」とカピレッシュは語る。カメラで取得した画像データからAIに農作物の情報を読み取らせることは簡単ではない。通常であれば、カメラの画像に映る農作物の形状や大きさが少しでも異なるだけで、AIは検知できず、適切にデータを取得できないのだ。
しかし、マクニカの開発経験がこれを可能にした。形状が異なるものでも一つの物体として認識できる「床の汚れを検知するAI」と、カメラとの距離が異なる物体に対してサイズを定量化して検出できる「ゴルフボールの自動検出AI」を活用し、半月というスピードで、農作物の大きさや色見などの情報を取得するシステムの開発と実装を実現させたのだ。
こうして、NEXTAGEとマクニカが共同で開発した生育データ可視化システムはまもなく世に出ることになった。このシステムが多くの農家で採用されれば、誰もが効率的に農作物の栽培計画(レシピ)を作成することができ、安定した高品質栽培が実現できることとなるだろう。


プロジェクトの展望
想いをテクノロジーで、「カタチ」にする
まだ誰も実現していない、困難なこのプロジェクトを前に進められたのはなぜか。それは、マクニカのAIに精通した「技」とNEXTAGEが持つ植物栽培における専門的な「知」が掛け合わさったからである。
NEXTAGEはおいしい農作物を作るノウハウには絶対の自信があったが、それを具現化するテクノロジーを持っていなかった。そこでマクニカが持つテクノロジーを掛け合わせることで、今までにないブレイクスルーを起こし、NEXTAGEの想いに応えたのだ。
「NEXTAGE様のように、『何とかして社会を変えたい』、『一人ひとりの人生をより良くしていきたい』という熱意やそれを実現するアイデアを持つ企業や人はたくさんいます。そのような方々の想いを具体的な『カタチ』として、社会へ実装し続けることが、私たちの使命だと考えています」と本村は語る。
このプロジェクトはマクニカが掲げる目標への大きな第一歩だ。マクニカはこのプロジェクトで新しく創り上げたビジネスモデルや技術、ノウハウを軸に、更に別の食糧問題の解決にも貢献していく。全ては、世界中の人々の健康的な生活の持続を実現するために。マクニカの挑戦は終わらない。

